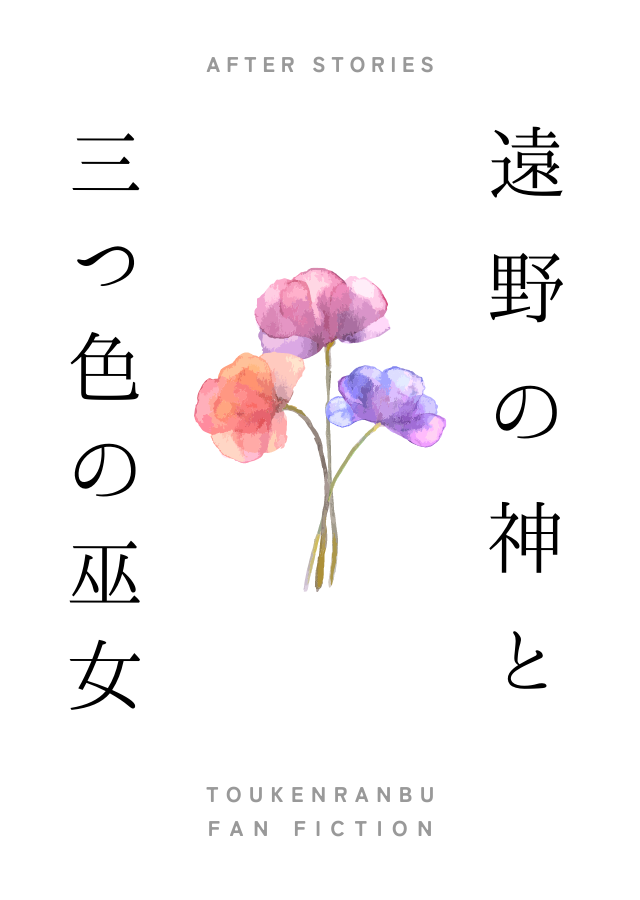独白
『――あんたはお兄ちゃんやお姉ちゃんと比べて、霊力はそんなでもないのねぇ。私とあの人の子なのに、不思議』
いつだったか、母があたしを見て困ったようにぼやいていた。また別の日には、近所のおばさんが小声であたしのことを噂しているのを偶然聞いてしまった。
『なんだか可哀想ね。大椙の本家の子なら、“適性さえあれば”緋袴の巫女さんになれたんでしょうに』
他の家であればいざ知らず、少なくともこの家では、霊力の強さがそのまま人材の価値に結びつくらしいと悟った。そういえば母自身も、「適性」があったから父に求婚されて一緒になったんだといつか話していた気がする。
だけど、母もおばさんもきっと悪気があってそう言ったわけではないだろうし、実際、家の中で特に邪険にされることはなかった。父は厳格で寡黙な人だけど家族への愛情はあったと思うし、母も明るくて優しい人だった。兄は家のしきたりで顔を合わせる機会が少なくなっても、何かとあたしたちを気にかけて連絡をくれた。姉はいつもあたしの相談に乗ってくれたし、あたしが落ち込んだ時にはそっと隣にいてくれた。何を話すでもなくただただ隣に座っていると、姉の心はしずかに凪いだ海みたいに思えた。……ちなみに、あんまり関係ないかもしれないけど、うちの神社の主祭神は「水」に縁の深い龍神様である。
そして、我が家の子ども五人のうちで一番年の近いあの子とは、いつも一緒だった。帰る方向が同じだからよく校門前で待ち合わせして一緒に下校したし、帰り道で色々な話をした。
ある日、二人で一緒に校門を出る時、遠くから数人の女子の視線を感じた。明らかにこっちを見て何かひそひそ話している。あたしはそれを無視して、「さっ、帰ろ」と彼女の手を引いた。
学校を出てしばらく歩いた頃、彼女が「ごめんね。私のせいで嫌な思いさせて」と申し訳なさそうにあたしに話しかけた。聞けば、彼女が小さい頃の怪我が原因で一部の教科を履修できないことに対して、心無いことを言う同級生がいるらしい。
「謝らなくていいんだよ。だって、なんにも悪いことしてないじゃない」
あたしがその同級生たちに対して憤ると、彼女はあたしのことを優しいと言ってくれた。
その時、内心戸惑って言葉に詰まったことをよく覚えている。彼女と話していると楽しいから一緒にいたというのも全然嘘ではないけれど、霊力の強い巫女である彼女を守るという役割を担うことで、家の中に自分の居場所が欲しいという気持ちがあったことも否定できないからだ。だから、あたしはべつに優しいわけじゃない。その後ろめたさがあたしの返答を鈍らせた。
だけど、とあたしは自分の心の奥底を覗き込む。あの子と一緒にいたのも、中学から剣道を始めさせてほしいと頼んだのも、紫紺の袴の事務員として大椙神社に関わり続けたのも、きっと、家の中での居場所をつくるためだけじゃなくて……。
――ああ、そうだ。あの子と同じように、あたしの記憶にも、やっぱり少しは欠けているところがあったらしい。あの最後の時に無意識下で願ったことを、今ようやく思い出した。あたしの、願いは――……
*
十二月三十日。最高気温は約二度、最低気温はマイナス四度。空気がひどく乾燥していて、日中でも北風が冷たい。
――あれからひと月あまり。しばらく日記を書く気にはなれないでいたけれど、久しぶりにまた筆をとってみようと思う。
今月の初め頃から、“あやめ”は本丸に現れない日が増えた。もともと毎日本丸に顔を出すという決め事があったわけではないけれど、それでもあやめもみかせも、これまでの約一年間はほとんど毎日のように本丸で過ごしていたのだから、この変化を単なる気の所為として片付けてしまうわけにはいかなかった。わたしは「その時」が近付いていることを悟った。
十日ほど前、冷たい雨が降る午後。数日振りに本丸に現れた妹は、いつものようにわたしの隣で出陣の指揮を見守っていた。敵の脇差が断末魔の叫びを上げ、黒い残骸となって霧散する。彼女はその様子を、いつになく真剣な表情でまじまじと見つめていた。
無事に任務を達成した刀剣男士たちに帰城命令を出して、出迎えの準備をしようと座布団から立ち上がった時、妹から話があると呼び止められた。その時、自分がうまく返答できたのかどうかは、今思い返しても解らない。ともかくわたしは、夕餉の半刻ほど前に執務室に来るようにと彼女と約束を交わした。
*
今日は、十二月……の半ばか後半。二十日くらいかな。
執務室で姉様と話をした後、部屋を出て扉を閉めると、ちょうど山姥切国広が階段を上がってくるところだった。彼はあたしの姿に気付くと、階段を上り切る前に足を止めてあたしを見つめた。山姥切も、どういう用件であたしが執務室に呼ばれていたかは知っているはずだ。
見つめ返した彼の目はわずかに揺れている。あたしと姉との話の内容が気になるけれど、そこまで踏み込んで良いものか……と思っているであろうことが手に取るように分かったので、あたしは先に口を開いた。
「……ちゃんとお別れしてきたよ。そろそろ行かなきゃいけないみたいだから行くね、って。あと、姉様は“こっち”には当分来ちゃダメだからね! って言ってきた」
姉は相変わらず、あたしたちの存在を本丸内で成立させるために自身の霊力の一部を割いてくれていたけれど、もうそうしてもらう必要はない。本来あるべき状態に戻ることに対する安心感と名残惜しさが綯い交ぜになったような、複雑な思いだった。
まだ俯いて黙ったままでいる山姥切に、あたしは改めて「あのね」と話しかける。
「あたし、命を落としてからこの本丸に来るまでの間に考えてたこと、うっすら覚えてるの。もう一回家族に会って話したいな、でも無理かな、って思ってたの。で、今振り返ってみたら、思いもしなかった方法でその願いが叶ってた」
そう話していると、この一年の間にあったことが瞬きのたびに頭の中を通り過ぎて行った。
「だから、何があるかなんて分からないんだから、また逢えるかもしれないよ」
この時、彼に伝えておきたくてこう言ったというのも本心だけれど、同時に自分にもそう言い聞かせたかったんだと思う。そこで、山姥切はやっと顔を上げてあたしの方を向いてくれた。
あたしは階段の途中にいる山姥切に向かって片手を差し出した。山姥切はその手を取ろうとしてくれたけれど、彼の手は空を切るばかりだった。あたしはもう自分の体をこの世に保つことができなくなっていることを知った。それでも、山姥切は握手するふりをしてくれた。
そして、彼は今度こそしっかり目を合わせて、一言だけあたしに伝えた。
「忘れない。――忘れるものか」
それに「ありがとう」と応えようとしたけれど、そう唇を動かす前に、あたしの意識は、切れ――
*
夕刻、鯰尾藤四郎と話をした。正確には、遠征から帰還してすぐに縁側で俺の姿を見つけた鯰尾が問答無用で隣に座ってきた、というところだ。
あやめが話していた内容を鯰尾に伝えている途中で、一時降り止んでいた雪がまたちらつき始めた。俺はそれを見上げながら、鯰尾にとも自分にともなく呟いた。
「少し、分かった気がする」
何のことだと鯰尾が問う。顔を上げて話し続けると、呼気が白く染まった。
「人間の言う、希望の存在だ。人もモノも、命がなくなったらそれで終わりだと、そう思っていたが」
鯰尾は、真っ直ぐすぎるほど真っ直ぐに俺を見つめながら話を聞いている。そういうところはあやめに似ている、という考えが頭の片隅に浮かんだ。
「また何処かで逢えるかもしれない――そういうのを、未来への希望なんて言うんだろうな。不確かな約束だとしても。人間も、我らも……心持つものは、それを糧に歩いて行けるものなんだろう」
鯰尾は俺に同意して、間断なく舞い落ちてくる雪花を眺めた。雲に覆われて姿は見えないが、もうじき今日の陽が落ちる。
*
「はー……。明日が本番だなぁ。今年も何事もなく終わりゃいいけど」
社殿の戸締りをしてそれぞれの家へ向かう帰り道、隣で兄が独りごちた。明日は大晦日。我々大椙神社の職員は、交代で仮眠をとりながら夜通し初詣客の対応に追われることになる。もう流石に慣れたとはいえ、わたしも兄も気合いを入れ直さなければ乗り越えられない日であることは間違いない。
――あの日以来、あの子が本丸に現れることはなかった。彼女がいないことで、本丸の中がこんなにも寂しく静かに感じられることを改めて思い知らされた。刀剣男士たちも、何もないところでふと後ろを振り返って、もういないのだと目を伏せるものが何振りもいた。
わたしは月曜からいつも通り仕事に出た。今が年末年始の繁忙期でよかったと思った。忙しくしているほうが却って気が紛れる。兄は初日にわたしの目が寝不足で赤いことに言及したきり、翌日からは普段通りに接してくれた。……敢えて、そう振る舞ってくれているのだと思う。
「そーいえば、昼間巫女さんたちが話してたの、お前も聞いてただろ。一月の休み、お前は何か予定あるの」
年末年始を越えて一月中旬に差し掛かったら、交代で休みを取ることになっている。言われてみれば、アルバイトの巫女さんたちが旅行に行く話や映画を観に行く話をしていた気がする。
「わたしは……おとしだま集め、ですかね」
「……は? お年玉を?」
「そう。御年魂を」
お年玉って集めるモンか……? と考え込んでしまった兄の隣で、わたしは低い雲の垂れ込める曇天を仰ぎ、白い息を細く吐いた。
その夜、わたしは抽斗から写真立てを取り出して、執務室の机の上に立てかけた。自分と妹が一緒に映った写真だ。わたしは机の上になるべく物を置かない主義だから、妹とのこの写真が、この部屋に初めて飾られたモノということになる。
灯りを落とした室の中、ラミネートされた写真が月光に照らされている。写真の中からこちらに笑いかけている彼女に向かって、わたしは「おやすみなさい」と呟いた。
厨
一月十一日。年始の繁忙も一旦落ち着き、今日は久しぶりの休日だ。普段よりだいぶ遅い時間に厨の入口の暖簾をくぐると、今朝の当番の薬研藤四郎と日本号が朝餉の洗い物をしているところだった。わたしが櫃からご飯をよそっているうちに、薬研が食卓に味噌汁の椀を置いてくれる。
礼を言って手を合わせ、椀のふちに口を付けた。立ち上る湯気と出汁の匂いに心が緩んだ。
朝餉を摂り始めてしばらく経った頃、ふと思い出したように薬研がわたしの方を振り返った。
「おっと、忘れてた。大将、その汁物、塩っ辛くなかったか」
わたしは少し考えてから首を横に振った。
「いえ。海鮮のよい香りがするとは思っていましたが……」
「そうだろ、そうだろ。この間貰った海老と帆立から出汁をとったからな」
薬研の隣にいた日本号も、肩越しにわたしを振り返る。
「それでな、味付けも俺がやったんだが、どうも晩酌のつまみを作る要領で、ちっと味を濃くしちまったみたいだ。すまんな」
わたしはそういうことかと相槌を打った。
「良い味ですよ。ゆっくり温かいものが食べられて有難いです」
窓の外からは、小鳥たちが挨拶を交わし合っているような長閑な鳴き声が聞こえる。
*
午後、お茶を淹れようとまた厨に立ち寄ると、秋田藤四郎と薬研藤四郎がひたすらキャベツを刻んでいるところだった。今日の夕餉はキャベツと豚肉を使った胡麻油鍋だそうだ。
「きゃべつは千切りにして、ふわっふわにするんですよ!」
「楽しみですね」
目を輝かせてわたしを見上げる秋田に、思わず頬が緩んだ。そして、自分の横に詰まれているキャベツの山に目を遣る。
「人数がいた方が早く終わるでしょう。包丁、もう一本ありますか?」
秋田の隣に座って無心でキャベツを刻んでいる最中、秋田が何かに気付いたようにわたしをじっと見て手を止めた。
「あれ? 主君はお料理は……」
わたしが迷い無く包丁を動かしているのを見て、違和感を覚えたものであるらしい。
「そういえば、そうだな。大将は歌仙と一緒によく皿洗いをしているから、厨に立っているところは何度も見ているが」
わたしは苦笑して頷いた。
「妹から聞きましたか。そうです、感覚で味を調えていくという作業が、昔からどうにも苦手で」
キャベツを一玉の半分まで刻んだところで一度手を止め、包丁を握った自分の手に視線を落とす。そして、一呼吸だけ置いて、包丁の扱いに慣れている理由を話し始めた。
「二年前のあの件からしばらく経った時……毎日何も手につかないのに、何か生産的なことはしていたくて。何となしに台所を覗いたら、母の背中が目に入って、その時から母の隣で食事の下拵えを手伝うようになりました。それで、野菜の皮を剥いたり刻んだりすることくらいは出来るようになったんです。……あの頃は、食材を前にしてもなかなか食欲は湧きませんでしたが」
母の隣で、二人分の包丁の音だけを聞いていた時の気持ちを思い出す。ちなみに、あの子たちの生前の記憶と矛盾することを恐れて、本丸に来てからは極力包丁を持たないようにしていた。
わたしの話を聞いていた薬研は「そうか……」と呟いた。秋田は、沈んだように下を向いてしまったが、その後、わたしを見上げて言った。
「……主君は、やっぱり優しい方ですね」
わたしが手元から目を離して秋田に目で問いかけると、彼は澄んだ瞳を細めた。
「きっと、子を亡くされた母君をひとりにしないように、そうしたんですよね? ひとりは、さみしいですから」
「…………」
わたしは応える言葉を見失ってしまった。代わりに、なるべく前向きに聞こえるようにさりげなく話をずらした。
「なので、これからはわたしも時々何か作ってみようと思います」
「本当ですか?」
秋田はやっと明るい声を取り戻した。
「主君、一緒に作りましょう。何がいいかなぁ」
簡単な料理について秋田と相談している途中で薬研の方を見てみると、薬研は何か言いたそうな顔をしてわたしを見つめていた。
*
その日の夕食はいつになく美味しく感じた。食後に少し休んでから、執務室へ続く階段を上がろうとしたら、薬研に声を掛けられた。
「大将。明日の出陣のことで、ちょっといいか」
わたしは勿論、と答えて、薬研を執務室に招き入れた。すると、彼は「休日なのに、出陣の話で悪いな」と言って、連隊戦終了までの出陣予定表を机に広げた。
「話っていうのは……明日の出陣をずらして、明日を休みにしないか、っていう相談なんだが」
「四部隊のうちのどこかに、出陣に障りのある者が?」
「いいや。ただ、俺たちを出陣させるだけでも大将は霊力を消費するだろう。……表に出ている以上に、疲れが溜まってきてるんじゃないかと思ってな。せめて、あと一日程度は休んで英気を養った方がいい。今だって、執務室に来たってことは、これから仕事しようとしてたんだろう」
図星だ。わたしが薬研の言を否定できず、視線を逸らしているうちに、薬研は予定表に手早く修正案を書き込み始めた。
「ほら、ここをこうずらせば、この日は出陣が一回増えるが、ここで回復できる。回復が間に合わなければ、他の短刀か脇差と交代してもいい。期間終了までには十分間に合うと思うぜ」
「そうすると、当初の予定よりは詰め気味になりますね。あなたたちの負担は……」
「何言ってるんだ、俺たちにとってはここが踏ん張りどころだぜ。大将に無理をさせるよりずっと良い」
薬研に苦笑しながらそう言われ、わたしは思わず目を伏せて考え込む。わたしの返事をじっと待ってくれている真っ直ぐな視線を感じた。やがて、薬研はわたしの迷いを汲んでか、改めて座布団に胡坐をかき直して別の話を始めた。
「……なあ、大将。さっきの、厨での話なんだが――味を調えるのが不得手だって言ってたな。それって、昔からずっとか?」
そう問われて、どうしてそんなことを、と首を傾げたが、わたしはここで、彼が近侍にも部隊の仲間にも声を掛けずにひとりで直接わたしのところに来た理由を察した。おそらくこの話をするためだ。そして――わたしには、確かに心当たりがある。
「そうですね……昔からですが、ずっとではなく、時々という表現が近いと思います。味見をしながら作れば上手く行く日もあり、全く味付けが出来ない日も」
薬研は「波があるってことだな」と相槌を打ち、考え事をするように顎に手をやって続けた。
「後者の日は……ここからは俺の想像なんだが、味覚が弱くなってるってことは無いか? 例えば、甘みだとか塩っ気だとか、一つの味だけが感じ取りにくくなる、とか」
「……あなたには、本当に隠し事が出来ませんね。その通りです」
身体的・精神的負荷を覚えた時、わたしの場合はそれが表情に出ることは少ないが、代わりに塩味だけが知覚しづらくなる。昔からそうだった。ただ、診断を受けたのは審神者就任の半年ほど前なので、比較的最近のことだ。わたしがそう説明すると、薬研は細長い溜息を吐いて頭を掻いた。
「やっぱりか。今朝、汁物の味の濃さに気付かずに飲んでたんで、もしかしてと思ってな」
あのやりとりだけでよくぞそこまで……とわたしが感心しているうちに、机に広げた出陣表が速やかに片付けられてゆく。
「今後症状が出そうな兆候があれば、疲労が溜まっていると思えばいい。休みづらかったら相談してくれ。無理が一番良くないからな」
薬研はそう言うと、冷えるといけないからと上着をわたしに寄越し、就寝の挨拶をして早々に執務室を辞した。
*
――薬研が忠告してくれた通りだ。疲労とは厄介なもので、しばしば眠気と不眠とを同時に引き起こす。この日も例に漏れず、身体はまだ休息を欲しているのに真夜中に中途半端に目が冴えてしまい、わたしは溜息をつきながら仕方なく寝室を出た。
厨へ水を貰おうと考えて西側の廊下に出たところで、一期一振と行き合った。彼はわたしの顔を見るなり、迷わず「眠れませんか」とわたしに訊いた。
「昨日よりはお顔の色が良くなられましたが、やはりまだお疲れのようですな。くれぐれもご無理はなさいませんように」
「……きょうだいですね」
思わずそう零すと、一期が何のことだと言いたげに首を傾げたので、わたしは意図を説明した。
「いえ、先ほど、あなたの弟がわたしに同じようなことを」
それを聞いた一期は目を丸くして、「そうでしたか」と苦笑する。わたしは、明日の出陣も取りやめて休みを貰おうと思っていることを彼に伝えた。一期は、それが宜しい、と安心したように頷いた。
「弟といえば……乱と骨喰が今日教えてくれたのですが、中庭で早咲きの梅が綻び始めたそうですよ。明日も天気が良いようですから、夜が明ければよく見えるかと」
一期はそう言って、まだ暗い中庭の方に指先を向けた。梅と聞いて、わたしはふと昔のことを思い出した。
「妹が、梅の花が好きだと言っていました。暖かい春を運んで来てくれる花だと。寒がりで、冬より夏を好む子でしたから」
一期の示す方を目で追って庭を見遣ると、暗闇の中に子どもの頃の彼女の姿が浮かび上がる。わたしはそれが単なる錯覚に過ぎないことを識っている。半端に眠ったせいで、夢の名残が幻を見せているのかもしれない。
「子どもの頃から、よく笑う子でした。それこそ、花が咲くような明るい笑顔で――花の名前を付けるなら、わたしなどよりも彼女のほうが余程ふさわしいのにと、よく思ったものです」
一期は肯定も否定もせず、ただ静かにわたしの話に耳を傾けている。
「本人にとっては色々悩みも多かったようですが、少なくとも、わたしはあの子の笑顔に救われていた」
わたしがそう話し終えると、一期は目を柔らかく細めてひとつ頷いた。
暗闇のなかの幻は既に消えていた。わたしは厨に向かうのをやめて、このまま寝室に戻ることにした。今度こそ深く眠れる気がした。西側の廊下を曲がり、自室の襖の前で立ち止まってみると、冷たい風のなかに確かに梅の花の香りが混じっていた。
呼ぶ声
一月中旬。今日は数日振りに本丸に現れることができた……らしい。数日振りというのは私が自分で判断したことではなく、偶然私を見かけた歌仙さんたちが教えてくれたことに過ぎないから、自分ではあまり実感がない。
連隊戦は現在終盤に差し掛かっていて、御年魂集めの進捗も順調だと聞いた。そんななか、今日は姉に代わって手入れ部屋に入り、御手杵さんの腕に包帯を巻いている。ちなみに、連隊戦は鍛錬扱いで、本丸に戻れば傷も癒えるシステムだから、これは連隊戦によるものではなくて、雪かきをしている途中で出来てしまった傷だそうだ。屋根に近いところにあった樹木の枝が服に引っかかって、梯子から落ちてしまったんだって。受け身が上手だったからか、落ちる時の悲鳴の大きさのわりには怪我が軽かったみたいなので、私はさすが刀剣男士だって思ったんだけど、本人は手入れをされている最中、「人の身の扱いって難しいんだなぁ~。まだ慣れねえよ」としょんぼり顔でこぼしていた。御手杵さんの場合、背が高くて手足もとても長いから、周りのものとの距離感をはかるのが他のひとよりも少し難しいのかもしれない。
「……はい、終わりました。これで大丈夫」
私は仕上げに包帯の巻き終わりのところを処理して、手入れの終了を宣言した。
「ありがとな。……お」
御手杵さんは包帯を巻いた腕を見て何かに気付き、嬉しそうに包帯の結び目を指差した。
「ここ、蝶々になってるじゃん。俺、主かあやめに手入れしてもらうことが多かったから、知らなかった。こんなとこにも、個性って出るもんだな」
ちなみに、主は結び目を内側に仕舞ってくれることが多くて、あやめはいつも、巻き終わりのところを“養生てーぷ”っていうやつで留めてくれてたな――。御手杵さんはそう続けた。
「そうだったんですね」
私は目を丸くして、改めて蝶々結びを見た。通常、手入れの作業を二人以上で行うことはないし、私たちの間で包帯の巻き方が話題になったこともなかったから、その情報は私自身も初めて知った。私たち三人から手当てを受けたことがある刀剣男士だから気付いたことなのだろう。
今度姉様たちに言ってみます、と返そうとして、下の姉とはもう会えないことを思い出し、私はそのまま目を伏せた。
「どうした?」
御手杵さんが座ったまま背を丸めて、私の顔を覗き込もうとしてくれているのが分かった。私は迷ったけれど、しばらくして重い口を開いて話し始めた。
「……夢を見たんです。姉様たちと……慶兄さんと史弦が本丸の裏手の原っぱで一緒に話していて、でも、そこに私はいないんです。自分の視点で見ているから自分の姿が見えていないというわけじゃなくて、四人とも、私のことが見えていないかのように話を続けていて」
御手杵さんは、うんうんと頷いて話を聞いてくれている。
「多分、そうだったら良かったのにっていう私の願望が見せている夢なんじゃないかしら。もし私がいなかったら、姉様の命は失われずに済んだかもしれない、って」
そうだ。私はその自責の念に耐えきれず、無意識に記憶に蓋をした。その記憶を取り戻してから、いつもどこかにその気持ちは巣食っていた。
御手杵さんは、うーーんと三秒くらい考えて、いつもより静かな声で心配そうに私に聞いた。
「それって、あやめにそう言われたのか?」
私は答えの代わりに首を振る。
「姉様は、『あの火事の時は、あたしがどうしてもそうしたかっただけだから』って」
でも、それは姉が私を気遣って言葉を選んでくれただけで、本当は……。どうしてもそんな考えが頭から離れなかった。
私の話を聞いてくれていた御手杵さんは、包帯を巻いていない方の手で頭を掻きながら言った。
「俺は、その場にいたわけじゃないから分かんねーけどさ。人間、生きるか死ぬかの分岐点で、自分が本心から望んでること以外を咄嗟に選び取れるとは思えないんだよな。何百年も人間っていう存在を見てきて、しみじみそう思う」
私は御手杵さんを見上げた。何かを懐かしむように遠くを見る彼の目に、名だたる武士の姿が映っているような気がした。
「自分が、本心から望むことを選び取る……」
私が彼の言葉を復唱すると、御手杵さんは私を見てまた一つ頷いた。
「ん。まあ、俺はそう思う、ってことだな」
そのまま手入れ部屋に敷いてある布団から立ち上がり、こちらに手を伸ばして、私が立ち上がるのを手伝ってくれる。私はありがとうございます、と御手杵さんを見上げた。そして――久しぶりに触れた人の手の温もりで、遠い昔のことを思い出した。
*
二〇一六年、一月十八日。本日終了となる連隊戦の報告書を長谷部たちと一緒にまとめていると、こんのすけが室に飛び込んできた。
「審神者様。審神者様ー」
鈴も鳴らさなかったところを見ると、相当焦っているようだ。わたしは彼にまず落ち着くように伝え、話の続きを促した。すると、彼は巻物を取り出し、その場にいる三名を見回しながらやや早口で告げた。
「異常事態です。時空の歪みが観測されました」
わたしと歌仙、長谷部はそれぞれ顔を見合わせたのち、矢継ぎ早にこんのすけに質問した。
「どういうことです?」
「歴史改変ではなく、時空の歪みかい?」
こんのすけは前脚で巻物の中の文字を指差し、首肯の代わりに一つ瞬きをした。
「はい。時間遡行軍が出現し、過去への攻撃を行っている……ここまでは通常の出陣時と同様です」
彼はそこから急に言いにくそうにして、おずおずと続けた。
「ただ、遡行軍が出現した時代というのが……」
わたしと歌仙は、こんのすけに促されて巻物を覗き込む。わたしは自分の目を疑いながら、報告書の文字を音読した。
「平成時代……。西暦、二〇〇二年……?」
隣で歌仙が息を呑む音が聞こえた。
「近すぎる」
「確かな情報なのか」
長谷部に問われたこんのすけは、申し訳なく思っている時にいつもそうするように、両方の耳をぺたんと前に倒した。
「ええ。最近時々あるんです。審神者候補者が直接狙われる事案が――」
――こんのすけの説明によると、最近は敵陣営にも「審神者という総大将が率いる刀剣男士たち」という存在が認知されてきて、歴史の転換点を直接攻撃するだけでなく、審神者の素質がある者が狙われる例が少しずつ増えてきている、とのことだった。『総大将は刀剣男士と違って只の人間だそうだから、そちらを叩いてしまった方が効率が良い』という発想なのだろう。特に我々の本丸は一度襲撃を受けているため、その時に倒しきれずに逃げおおせた敵の残党から情報が漏れやすくなっていたらしい。今風に言えば、セキュリティが脆弱な状態になっていたということだ。こんのすけが申し訳なさそうにしていた理由はこれだった。
ただし、遡行経路が未だ確立されていない平成という時代には、こんのすけ曰く『飛びにくい』らしい。それは遡行軍にとっても同じなので、今回現れた遡行軍の頭数はそう多くないだろう、とのことだった。ただ、たとえ敵が一・二体だとしても、人間である審神者一人を始末するには十分すぎる力を持っているため、放置も楽観視も危険である。
「直近の時代であればあるほど、時間遡行のための通路が狭いのです。この出陣先であれば……そうですね、適正練度は……」
こんのすけはどこからか取り出した半透明の端末を前脚で器用に操作して、今回の出陣における練度制限を割り出した。出陣に際しては、各合戦場ごとに練度制限が存在する。例えば「維新の記憶」の函館であれば、部隊員全員の練度を足した数が十一以下でないと、システム上出陣不可能となる。
「…………」
端末を操作していたこんのすけの右手が止まり、耳と尻尾は困惑を表すように垂れ下がった。わたしも長谷部と歌仙の方を向いて、もう一度お互いに顔を見合わせた。
モニターに映し出された練度制限の数値は――『二』。
*
平成二十八年、睦月の……ええと、何日と言っていたっけ。まあいいか。多分、月の半ばくらいじゃないかな。
僕ら兄弟は一日違いでこの本丸の審神者に顕現され、昨夜の挨拶を経て、今日はまず本丸の中を見て回るように言われていた。案内役だという脇差の子に伴われて、本丸内を西からぐるりと一周する。
中庭に面した座敷の部屋を通りかかると、障子が片方だけ開いていて、部屋の中で三人と一匹が顔を突き合わせているのが見えた。その様子を不思議に思って何となく立ち止まってみると、上座に座っていた審神者の女性とちょうど目が合った。
「髭切……膝丸」
彼女は何かを考えるように顎のところに指を宛ててそう呟くと、何かを思いついたとばかりに、その場にいた他の二振りに目配せをした。
「……それで、今回の制限練度は合計二。練度二の者を一振り、または練度一の者を二振りまでしか現地に送り込めないようなんだ」
この本丸の一番刀らしい兼定派の刀が、まだきょとんとしている僕たちに経緯を説明してくれた。なるほど、早い話が、僕たちの初陣はその平成十四年という合戦場になるということだね。そう確認すると、審神者から是という答えが返ってきた。
「まだ人の身に慣れてもいないでしょうに、このような特殊な戦を初陣にしてしまって申し訳ないのですが」
彼女は切れ長の目を伏せてから、改めて顔を上げて言った。この本丸には現在、練度が一か二の刀はあなた方しかいないので、力を貸してもらえないか、と。
正直、まだよく分かってはいないけれど、そう言われては特に断る理由もない。僕は隣に座っている弟と目を合わせて一瞬で意思を確認し、すぐに「構わないよ」と頷いた。
*
事前に聞いていた通り、平成時代への遡行経路とやらはやけに狭かったし、そんなに居心地の良いものではなかった。思わず強めの瞬きを数回繰り返す。すると、いつの間にか、開けた空地のようなところに自分たちが立っていることに気付いた。目的とする時代に到着したということかな? 弟と一緒に時空の座標を確認すると、演算で割り出した地点からそう外れてはいないようだった。
「ひとまず、目的地への転送は成功したようだな、兄者。さて……」
弟は片手を腰に当てて辺りを見回した。ここは仕切りに囲われた草原で、鮮やかな色に塗られた小さな矢倉のようなものがあったり、動物の置物が二つ三つ並んでいたりした。傍らの石碑に公園という文字が刻んであるので、公の場所であることは間違いないらしい。
「時間遡行軍は、もうこの辺りにいるのかな」
普段であれば審神者と隊長の間で意思疎通ができるようなんだけど、今回は強制帰還以外の命令は不可能らしい。
「ああ、索敵と並行して、守護対象の審神者候補者を探さねば」
そう話しながら、まずは広場を出て、灰色の道なりに北へ進むことにした。しばらく歩いているうちに、白い大きな建物が見えてきて、その付近から大勢の子どもらの話し声が聞こえた。思わずそちらに目をやると、その建物から、黒や赤の行李を背負った子どもたちが続々と出てくるところだった。
僕たちは一旦物陰に隠れて様子を窺うことにした。漏れ聞こえてくる会話を聞くに、彼らはこれからそれぞれの家に帰るところみたいだ。
「……そういえば、今回敵に狙われている審神者候補者って、小さな女の子だと言っていたよね。どういう子かまでは分からないけど」
「となると、あの子どもらの中のどこかに……?」
僕たちは小声で話し合い、白い建物から出てくる子どもたちを一人ひとり注視しようとしてみた。時間遡行軍の脅威になるほど霊力が強い子なら、たぶん、僕たち刀剣男士にも何らかの方法で見分けられるものなんだと思う。なぜだかそんな確信があった。
しばらくして、人波があらかた落ち着いて辺りが静かになり始めた頃、建物の門を通って歩いてきた一人の女の子と目が合った。僕たちは遡行軍に存在を気取られないように極力気配を消しているし、まして人の子であれば尚更見つけづらいはずなのに、彼女は迷う様子もなく、ただそこにあるものを見て、それが人型をしていたから目を合わせてみただけ――という感じだった。
この子だ、と思った。僕が隣の弟にそれを耳打ちしようとした時、にわかに空が曇って空気が濁った。
『ミツケタ、ゾ……』
すぐそばで、地の底を這うような重苦しい声が聞こえた。刀の柄に手を掛けて振り返る。ちょうど遡行軍の大太刀が天高く振りかぶられ、その攻撃を弟が受け止めようとしているところだった。そこに加勢しようとしたら、大太刀の脇から短刀二振りと脇差が滑り出てきた。
「おっと」
そのまま刀を薙いで脇差を処理したものの、短刀たちは刀の切っ先を回避して僕の横をすり抜けて行ってしまった。行き先は言わずもがな、さっき目が合った女の子のところだろう。後ろを振り向くと、女の子は驚いた顔をして道の真ん中で立ち竦んでいた。
「兄者、そちらを頼む!」
大太刀と切り結びながら弟が吼えた。わかったよ、と弟に聞こえるように返事をして、短刀の片方を刀で突く。次いで、もう一振りの短刀に狙いを定め――ようとしたところで、女の子の背後に太刀型の遡行軍がいることに気付いた。
「おいで」
彼女の手を引いて外套の中に誘導する。もう片方の腕で敵の太刀の攻撃を受け止める体勢をとったけれど、そうはさせまいと、竜骨型の短刀が僕の視界を邪魔するように纏わりついた。その短刀の方に気をとられた一瞬の隙に、敵の太刀が間合いを詰めてきた。
あ、やられる。刀を構える時間はない。僕は外套の中の女の子を守ることを優先して、受け身を放棄することにした。斬撃音と、肉が断たれる感触と、灼け付く痛み。体温よりも少しあたたかい液体が後から後から出てきて零れ落ちている、と何処かひとごとのように考えた。
「兄者。大丈夫か」
弟の声が遠くに聞こえた。いや、案外近くにいるのかもしれなかった。僕は辛うじて返事をして、「まだその辺りに何体か隠れているかも」と報告した。
「困ったな。思ったよりも頭数が多いね」
刀を構え直してみるも、今の状態だと鍔迫り合いで圧し負けるだろうな、と直感した。
「ここは任せてくれ。兄者は、その子を守りながら出来るだけ遠くへ」
弟が僕の肩に手を置いて囁いた。その手の甲にも、傷跡や血を擦った跡が見える。
それ以上問答している余裕はなかった。僕は働きが鈍りつつある頭で何とか頷き、女の子をよいしょと抱きかかえて、ほとんど本能だけで刀を振って短刀を始末しながら「頼んだよ」とその場を後にした。
遠くと言っても、土地勘の無い町のこと、あまり離れると後で合流するのが難しくなるし、何より点々と滴る血の跡が道標になってしまうから、攪乱の効果はほとんど無いだろう。時間遡行軍の知能がどれほどのものかは分からないけれど、少なくとも最初に遭遇した大太刀は検非違使と同じく口を利くことができるようだったから、たぶん血の跡を辿るくらいの知能は持ち合わせているんじゃないだろうか。ああ、それにしても、止血の方法くらい教わっておくべきだったかな――。そんなことをぼんやり考えながら、自分と女の子のふたりが隠れられそうな場所を探した。
南に少し歩いて、僕らが最初に降り立った広場が見えてきた時、ふと、朱色と空色と桃色に塗られた小さな矢倉が目に入った。あそこなら、一時的に隠れられるかも。僕はかがんで矢倉の下に入り込み、女の子を地面に下ろして、彼女の衣服の肩口を払ってあげた。砂埃は付いてしまったけれど、血は女の子にはそれほど付いていないみたいでほっとした。
「怪我はしてないよね?」
頭を撫でながら訊いてみると、すぐに頷きが返ってきた。女の子の視線はそのまま、血塗れになった僕の左半身に移った。
「……おにいさん、だいじょうぶ? いたい?」
彼女は白い手巾を取り出し、それを僕の腕に巻いて止血しようとしてくれた。不思議なもので、手巾を巻かれた辺りだけ、本当に痛みが少し和らいだ気がした。
女の子と小声で二言か三言くらい話しながら、頭の片隅で色々なことを考えた。途中で外套の中に隠したとはいえ、至近距離で遡行軍の姿を見てしまって瘴気にも触れただろうに、叫び出さなかったこの子はえらいな、とか。できれば弟の加勢に行きたいけれど、この分だと流石にしばらく立ち上がれそうにない、とか。人の身というものは、血を流し続けると、こんなにも……感覚がぼんやり、してくるものなのか……とか……。
意識を手放す直前で、僕を探す弟の声が聞こえて目が覚めた。ここだよ、と答えようとしたけれど、腹に力が入らなくて声が出なかった。無理にでも声を出すためによいしょと体勢を変えた時、ちょうど弟が片膝をついて矢倉の下を覗き込んでくるのが見えた。
「ここにいたのか、兄者」
弟は、終わったぞ、と言ってこちらに手を伸ばした。ああ、その子を先に引き取った方がいいか――そう言って弟が女の子に触れようとした瞬間、僕は咄嗟に彼女を抱き寄せて目隠しをして、右手で刀を逆手に抜き、そのまま――弟の胸の中心目掛けて突き刺した。僕の外套の中で、女の子が目を丸くして僕を見上げてくる。
「ああ、ごめんね。耳も塞いでおくように言っておけばよかったね」
出陣先でやむをえず現地の者と接触してしまった場合、その後、歴史の修正力が働いて緩やかにそのことを忘れていく場合が多いと聞いたけれど、さて、この子の中に今日の記憶はどのくらい残るのだろうか。そんなことを考えた。
弟の形をしたものは苦悶の咆哮を上げて文字通りばらばらに崩れ落ち、それらの破片がいつの間にか再構成されて、禍々しい妖気を放つ時間遡行軍の姿になった。
『ナゼダ……ナゼ、ワカッタ』
「…………」
さっきの一突きのためにわりと限界まで力を振り絞ってしまったから、その疑問に答えてあげる体力はもう残っていない。それにしても、まだ喋れるということは、さっきの攻撃では無力化するには足りなかったということだ。まずいな、ほんのあと一太刀、背中から斬られでもしたら、折れ――
「――兄者!」
ああ、よかった、今度はちゃんと本物だ。僕は返事をする代わりにひとつ息をつき、敵に向けていた刀をようやく下ろした。
「すまない、あと一息のところで大太刀を逃がしてしまった」
弟は口惜しそうに言いながら、大太刀の体に沈めた刀を横薙ぎに抜いて、刀身の血振りをした。彼も動けないというほどではないようだけれど、明らかに息が上がっていたし、体の至るところに傷が見えた。僕たちは、断末魔の叫びを上げていた大太刀が黒い砂のようなものに変じてすっかり消え去るまでを見届けて、それから刀を鞘に収めた。
その時、遠くから誰かの名を呼ぶ声が聞こえてきた。女の子の声だ。
「……すず。いすずー?」
しばらく様子を見ていると、その声がこの広場にだんだん近付いてくることが分かった。
いすずって、君の名前? 女の子にそう尋ねると、彼女は無言で頷いた。
「そうか、迎えが来たか。何よりだな」
弟も満足そうにして、声が聞こえる方を眺め遣っていた。
「ほら。お行き」
僕は彼女の背中に掌を添えて、広場の出口の方に誘導してやった。
「うん。ありがとう、おにいさんたち」
女の子は僕たちを振り返り、律儀にお辞儀をして、彼女を捜しに来た人の名を呼びながらそちらに向かっていった。ふたりが並ぶと、審神者候補の女の子のほうが少し小柄に見えた。僕たちは、仲良く手を繋いで遠ざかっていく彼女たちの姿をしばらく見送った。
「顔立ちが似ているな。友人かと思ったが、姉妹だろうか」
弟が意外そうにつぶやいた。うーんと考えて答えようとした時、本丸への強制転送が作動して、僕らの身体と意識は徐々に時空の狭間に引っ張られ始めた。ただ、視界が閉じる直前に見えた、橙の絵具で空を塗ったような落陽の風景だけが目に焼き付いた。
*
「髭切、膝丸。お疲れ様でした」
「こちらのモニターでも、時空の歪みの消滅が確認できましたよ! 未来の審神者候補の少女を守るという任務は成功ですね」
「ああ。俺たちが見てきた範囲でも、敵の気配はもう無くなっていたように思う」
手入れをしてもらった後、僕たち兄弟は審神者の部屋に呼ばれて出陣の成果を報告した。
ふと主の手元に目を落とすと、報告書の隅に審神者の署名が見えた。僕は「ああ」と言って、上向きにした掌をもう片方の拳で打った。
「そうだ、どこかで聞いた名だと思っていたんだよ。君の名前だったんだね。ということは、あの審神者候補の女の子は、子ども時代の君かな」
そう尋ねると、主は記憶の中から心当たりを探すような顔でひとつ瞬きをした。彼女が口を開く前に、弟が「そういえば」と付け足した。
「あの時、姉らしき少女が迎えに来ていたな。主、君にもきょうだいが?」
「いえ、わたしには姉は居な……。……ああ」
主は急に何かに気付いたように動きを止めて筆を置いた。
「すみません。あなた方には顕現直後にこの任務に当たってもらったので、わたしたちのことについて、まだ説明をしていませんでしたね……」
主が居ずまいを正して話を続けようとしたところで、室の外から誰かの声が聞こえた。
「姉様。入ってもいい?」
あれ、と思った。鈴が鳴るような声。それこそ、こんな風に鳴る声を最近どこかで聞いたような。
僕と弟が顔を見合わせているうちに、主が入室を許可して、声の主が姿を現した。緋袴を着けた小柄な女の子だ。その子は僕と目が合うと、驚いた顔のまま一瞬固まり、口許を抑えて「あっ……」と小さく声を漏らした。
詳しい事情は分からないけれど、その反応が答えだということはすぐに分かった。僕は笑って胸元から白い手巾を取り出し、やっと返せるね、と言って彼女にそれを手渡した。
「あの少女は……主ではなく、主にとってきょうだい同然の従妹君だったのだな」
主の話をひととおり聞いた後、自室に戻る途中の渡り廊下で、弟がぽつりと呟いた。そうだね、と相槌を打つと、弟はその場で一旦立ち止まって僕に訊いた。
「兄者。今回の任務、『甲斐が無かった』と思うか」
結果として、あの緋袴の少女は審神者になる前に命を落とした。もっとも、その運命が巡り巡って、主が審神者業を引き受ける動機に繋がりはするのだけど、それでも。
「まさか」
僕は弟を振り返ってすぐに答えた。
「僕たち刀剣男士の本分は、人間の在るがままの歴史を守ることだからね」
それを聞くと、弟は僕をまっすぐ見つめて、言葉を噛み締めるように息を吸い込み、力強く頷いた。
「それに、見ただろう、主があの娘に向ける目を。きっと、あれが答えだよ」
彼女の涼しい瞳に優しい色が混ざった瞬間を思い出しながら、僕は渡り廊下から見える西の空に目をやった。弟も僕の視線につられて同じようにした。燃えるような太陽が山の端にかかり、今にも沈みゆこうとしていて、辺りは絵具を塗ったように橙の色に染まっていた。
「ああ。……同感だ」
弟は、夕陽に向かって言っているのか僕に言っているのか分からないような調子で、感嘆の溜息とともに一言そうつぶやいた。僕たちはしばらくそのまま立ち止まって、太陽が山の向こうに沈んでしまうのを見届けた。最後の残滓が山の稜線を輝かせて、やがてその光も静かに消えていく。それを合図のようにして、僕は「さて」と渡り廊下の先の方に足を向けた。
「それじゃあ、行こうか。えーーと……。脛…………丸?」
「部位が違うな……。兄者よ、いつになったら俺の名前を覚えてくれるのだ……俺は悲しいぞ……」
「えー、でも、おまえのことを間違えたりはしなかったけどねえ」
名前よりも、そっちの方が大事なことじゃないかい? そう続けると、弟は「何の話だ」と首を傾げた。僕はその疑問には答えてあげないことにして、薄暮の空を眺めながらのんびりと自室へ歩き始めた。
*
――その夜、夢を見た。今日髭切さんと膝丸さんに会ったことではっきり思い出した、あの日の出来事をなぞった夢だ。まだ七つか八つくらいの時、私は恐ろしい妖に追われていて、知らないお兄さんたちが助けてくれて……。そして、私がなかなか待ち合わせ場所に来なかったので、従姉が辺りを探しに来てくれたのだった。夢は従姉と私が並んで歩いているところから始まっていて、私は幽体離脱でもしたように、子どもの頃の二人を外側から見ていた。
髪を青い結紐で一つに結んだ女の子が、もう一人の女の子に手を差し出しながら言った。
『もう、しんぱいしたんだからね。たくさん歩けないのに、かってにどこか行ったりして……』
手を差し出された子は、ごめんね、と言ってその手を取る。二人の背格好はそれほど変わらないけれど、背丈も歩幅も一つ結びの子の方がちょっとだけ大きい。その子は、兄様も姉様も心配してるわよ、と続けて、繋いだ手を改めて握り直した。
『――ねえ、いすず。あたしたち、ずっとこのまんまでいよう。おたがいに、手をはなしちゃだめだよ』
いつか大人になっても、ずっといっしょにいるの。約束ね――。そう言われた女の子の方も、『うん、わかった。やくそく』と嬉しそうに頷いた。
二人は内緒話をするように顔を寄せて笑い合い、繋いだ方の手を歩くリズムに合わせて揺らしながら、肩を並べて通学路を歩いていった。
その後ろ姿を見送ったところで目が覚めた。緩慢な動作で身体を起こす。辺りはまだ暗いどころか、夜半にもなっていなかった。東向きの部屋には、弓張り月の光だけがぼんやりと差し込んでいる。私は目尻に出来ていた涙の跡を指で拭い、胸の前で両手を組み合わせて握り込んだ。
「……ずっと、離さないでいてくれたんだね」
小声でどこにともなく呟いた独り言は、冬の夜の冴え冴えとした静けさのなかに燻るように溶けていった。
花の雨
睦月の晦。本丸の庭には、薄紅の花が見事に咲き誇っている。主は本丸内と外界との気温差を抑えるために、平時は外界と連動した景趣を設定されているが、このところは、桜を好まれるみかせ様のために春の景趣を選択されている。その影響で、今日の陽光は一足早く春が訪れたようにあたたかい。
日当たりの良い縁側で、みかせ様と並んで腰掛けた。――思えば、この一年の間、よく彼女と此処で茶を頂きながら庭の様子を眺めたものだった。不思議と話が尽きて困ることもなく、かと言って、しばらく互いに黙っていても居心地の悪さを感じることもなく、肌寒い日でも心だけはあたたまるような時間だった。
不意に、みかせ様が細い声で私の名を呟かれた。返事をすると、少しだけ話をしても良いかとみかせ様は仰った。
「……実を言うと、記憶を取り戻してから、ずっと心のどこかで考えていました。私がいなければ、姉様はまだ生きていてくれたのかもしれない、って。それなら、私がいない方がよかったんじゃないかって」
私は、そのようなことは――と言いかけたが、みかせ様はそれを押し留めるように静かに微笑まれ、首を横に振った。
「だけど、今はそうは思いません。姉様たちと一緒に暮らしてきた日々も、一期さんや皆とこの本丸で過ごした時間も、全部私の大事な思い出だもの」
私はほっと息をついて首肯した。それを確認して、みかせ様はまたそっと目を伏せる。
「本音を言うと、この先、私のことを思い出した誰かに淋しい顔をさせてしまうくらいなら、忘れられてしまってもいいっていう気持ちはまだあるんです」
言いながら、彼女は緋袴の上に置いた両の掌を見つめた。そこに一片の花弁が音も無く落ちた。
「でも、同時に、私が姉様や皆のことを愛していたことだけは憶えていてほしい、とも思っています。もし、何かを願うことが許されるなら、私は……その気持ちひとつだけ、此処に残していきたい」
いつもご自身のことを措いてでも周囲を気遣われていた、彼女らしい望みだと思った。
「忘れられてもいいのに憶えていてほしいなんて、矛盾していて変だと思いますか? だけど、どちらも私の素直な気持ちです」
彼女は私を見上げ、目を合わせて笑みを深めた。
中庭に花が舞うのをふたりで眺めているうちに、彼女は眠気を誘われたようで、瞼をゆっくり数度閉じた。私がどうぞ、と自分の肩口を軽く叩くと、みかせ様は私の肩にそっと頭を凭せかける。
彼女はついに完全に瞼を閉じ、かすかな寝息を立てて微睡み始めた。風に乗って飛んで来た花弁の軌道を辿って彼女の緋袴に視線を移すと、みかせ様の手が袴の上に綺麗に揃えられているのが見える。彼女の細い指は、文字通り透明に透き通っていた。その光景は、そのまま私たちに残された時間が少ない事を示している。
彼女の耳に聞こえていることを願いながら、私は語りかけた。
「私は、貴女と出会えて幸せでした。今代の私の主は、あやめ様、みかせ様、五鈴様のお三方です。これからも、ずっと」
次に隣を見た時、既に彼女の姿は無かった。代わりに、風が運んで来た桜の花弁が何枚か吹き溜まって、板張りの上に薄紅色の模様をつくっていた。しばらくぼんやりとそれを眺める。もう一度風が吹いて板張りの上の花弁を散らす頃、背後の障子が静かに開いた。畳を擦る足音がする方を振り向くと、月白色の衣の裾が見えた。江雪殿は、私と茶が載った盆との間に不自然な空間があることで何が起こったかを察したらしく、名残惜しそうに呟いた。
「姫は、旅立ちましたか」
私は、はい、と短く答える。
「また……寂しくなりますね」
「ええ。……ですが、その寂しさごと、全て私たちが憶えていましょう」
江雪殿と共に縁側から空を見上げた。薄紅色にけぶる中庭の景観のなか、桜の樹に止まっていた萌黄色の小鳥が短く一声鳴いたかと思うと、瞬く間に薄雲の向こうへ飛び去ってしまった。
*
一月三十一日。就寝前、わたしは階段をのぼって、執務室の灯りをつけた。机の端の写真立ての隣にもう一枚の写真を置くと、木材と陶器が触れ合う時の丸い音が小さく響いた。わたしはしばらく二枚の写真を見つめてから、親指の腹で額縁を撫でた。
開け放していた東側の窓から、無遠慮に風が吹き込んでくる。――ああ、そういえば一時的に春の景趣を設定していたのだった。わたしは窓を閉めに来たことを忘れて、雨のように花弁が散りゆくのを一人でずっと眺めていた。
泡沫
如月の十八日。この本丸に来てから一週間目。
洗濯物が乾いたのを確認して、きちんと四角に畳んだ。これで最後。さっき堀川国広さんが洗濯物の取り込みを手伝ってくれたから、予定よりも早く終わった。あ、堀川さんといえば、顕現直後にご挨拶した時に「初めて会った気がしない」と言ってくれたのをよく覚えている。あれは、自分もお手伝いが好きだから性格が似ているっていう意味だったのかな? それとも、演練で会ったことがある別の本丸の物吉貞宗のことを言っていたのかも。
この本丸では、ここ半月、出陣や遠征を控えている。主様の妹君と従妹君がもともと本丸によく出入りしていたんだけれど、彼女たちが向こう側に旅立たれてしまったからだそうだ。それで、本丸内の霊力が安定するまでは、しばらく鍛刀や内番をこなして日々を過ごしているんだと、近侍の長谷部さんが教えてくれた。
内番を終えて、広いお屋敷を見渡してみる。本丸のそこかしこに、ひっそりと雪のような寂しさが積もっているように思えた。渡り廊下から母屋に戻る途中に中庭の方を見たら、紫紺色の夜空に真っ白に輝く月が浮かんでいた。今夜は、弦が少し膨らんだ弓張り月だ。――あの月の、残りの半分はどこに行ったんだろう。今は見えないその半分の月のことが、何だか気になった。
*
翌日、十八日。
「三か月前の霜月のこの地方に出陣、ですか?」
思わず目をしばたたいて主様に確認した。主様のお話はこうだった。去年の霜月、この本丸が襲撃を受けた日の歴史に綻びが生じている。その日は、本丸が落とされる前に何とか敵を殲滅できたのだけれど、敵はそこに追加戦力を投入して、今度こそこの本丸を攻め落とそうとしているのではないか――。
ただ、遡行先の時代が近すぎると、遡行経路も狭くて不安定になるし、練度制限もある。それに、同じ刀剣男士どうしの鉢合わせを避けないといけないので、当時この本丸にいた刀剣男士を送り出すことはできない。だから、まだ一度も出陣させていないあなたにしか頼めない、と主様は仰った。
「わかりました! 大丈夫ですよ。皆さんに幸運をお運びする刀なんですから」
いくさでお役に立てるのは嬉しい。ボクには他の選択肢は無かった。主様に笑いかけたら、主様も頷いて、つられたようにわずかに微笑んでくれた。
*
遡行経路を抜けると、本丸の西門近くの森の中に出た。
「うーん。誰もいない……。まずは偵察を進めないと」
神経を研ぎ澄ませて微かな音と気配を辿り、深い木々の間を進んだ。辺りはやけに静かで、ただ自分が草を踏み分ける乾いた音だけが聞こえていた。敵の気配はまだ遠く、あちこちに散らばっている。
本丸の周囲をぐるりと回って正門の鳥居の近くに差し掛かった時、急に気配が濃くなった。なるべく足音を立てないように走って、物陰から様子を窺った。
薙刀型の敵が一、二……三体。鳥居の向こうには大太刀もいる。敵から目を離さないようにそっと距離を詰めていくと、刀剣男士が大太刀と切り結んでいるのが見えた。あの素早さは、たぶん脇差だ。劣勢のようだったので、こっそり近付いて薙刀の背後をとった。
「よーし、やっちゃいますよ!」
人の身で戦うのは初めてだけれど、どう動けばいいかは不思議と身体が覚えている。視界の端で、堀川国広さんが目を丸くしているのが見えた。さっき見えた脇差は、堀川さんだったんだ。
薙刀に封じられていた視界が開けて一気に動きやすくなり、形勢は有利に転じた。体格差があっても、速さと押し出し力なら脇差に分がある。一対一での鍔競り合いを制し、敵が次の攻撃のために得物を振りかぶっている間に、一気に間合いを詰めて懐に入った。
「――幸運は、いつもここに!」
敵の心臓めがけて深く刀を差し込むと、薙刀は断末魔の叫びを上げて、黒い霧に変わった後に消えてしまった。
「ありがとう。助かったよ。あなたは?」
「ええっと、他の本丸の刀、です。たまたま近くを通りかかったので、お手伝いを」
今回は本当の事情をお話してはいけない決まりなんです、ごめんなさい。心の中でそう謝りながら、堀川さんににっこり笑いかけた。堀川さんは、余計なことを考えていられないこの状況だからか、怪しむこともなく受け入れてくれた。
堀川さんの話によると、骨喰藤四郎さんと厚藤四郎くんが森の東のほうで敵を食い止めているそうだ。そっちに応援に行ったほうがいいかな、とふたりで移動を検討したけれど、この中央の入口付近の持ち場を空けるのもそれはそれで危険だ。それに、よく見ると堀川さんの腕や脚は怪我だらけで、疲労も酷いみたいだった。
「ここ一帯を索敵してきたんですけど、敵の気配はこの正門辺りが一番濃かったので、後続があると思います。それまでに、少しでも体力を回復しておきましょう」
ふたりで目立たない草叢に隠れて、出来る限りの応急処置をした。主様が持たせてくださったお水を堀川さんに分けてあげると、彼の疲労はだいぶ回復したみたいだった。
堀川さんは懐から小さな包みを取り出し、掌に載せてじっと眺めた。それを見て「御守りですか?」と尋ねたら、堀川さんはにっこり笑って頷いた。
「作ってもらいました。これを見ると、絶対に主さんたちの元に帰るんだ、って思えるんです。御守りって、折れそうになった時に作用するものだと聞いてますけど、それ以外にも効果があるのかも」
「主様たち……って、三人いらっしゃるんでしたっけ」
そう言うと、堀川さんは頷きかけて、はたと気付いたように首を捻った。
「あれ? 審神者と刀剣男士の仲間のことを言っている、って受け取られると思いましたけど、よく分かりましたね。主さんが一人じゃないってこと」
「あっ……」
えへへ、と笑って誤魔化すのが精一杯だった。不自然に思われない程度に、更に質問を重ねてみる。
「どんなかたなんですか?」
「ええと、冷静で……でも冷たくはなくて優しい女性と、元気でお転婆な女の子と、引っ込み思案で細やかな女の子。こう言葉にしてみると、三人とも全然違う印象ですね」
そう語る堀川さんの顔を見ていると、それだけで主様たちとどういう関係なのかが窺い知れる気がして、思わず笑みがこぼれた。
「主様たちが大好きなんですね」
堀川さんは、そんなに顔に出ていたのかな、と少しだけ面映ゆそうに呟いたけれど、すぐに微笑んで頷いた。
「主さんの采配を信用しているのももちろんだけど、雪が積もった日に一緒に雪うさぎを作ったり、裁縫道具を拡充するならどんなのが欲しいかを相談したり……そんな日々の小さなことでも心が温かくなるんです。あのひとたちの目に映ることそのものが嬉しい、っていう感じかな」
彼が話す様子をじっと見つめて、一言ひとことに耳を傾けた。お会いしたことがないはずの妹姫様たちが、あの本丸のなかで生き生きと日常を過ごされているご様子が瞼の裏に見えるみたいだった。
それから、堀川さんは人差し指を立ててこんな話をしてくれた。
「日課で刀解をするでしょ。余った刀を火にくべる時、まるで広い海に投げ捨てられるみたいだなって時々思うんです。うっすらとしか覚えていないけど、僕には暗い海の底にいる記憶があるから。深く沈むにつれて、地上の景色がゆらゆら歪んで段々遠ざかって、白い泡沫が浮かんでは消えていって……」
ボクが相槌の代わりに瞬きをしたのを確認して、堀川さんは口の端っこをわずかに上げた。
「それを思い出した時、気付いたんです。ああ、見つけてくれた人がいるから、僕がここに存在できるんだ、って」
堀川さんはそう言って、木々の間から垣間見える空を仰いだ。夕暮れ近くの橙がかった陽光が、彼の瞳にきれいに反射している。
「人が紡ぐ歴史が、僕と出会った人の眼差しと心が、刀剣男士である僕を作った。トシさんや、相棒の兼さんや、主さんたちや、仲間のみんなが、僕をここに存在させてくれた。だから、守りたいんです。泡沫のように無かったことになんてしたくない」
いつの間にか、時間遡行軍の気配が濃くなっていた。堀川さんは刀を構え直しながら、横目でボクに目配せした。
「さて。ここを無事に切り抜けられたら、うちの主さんたちを紹介させてくださいね。危ないところを助けてもらったんだから、お礼もしなきゃいけないし」
――もし本当に妹姫様たちにお会いできるのなら、どんなに良いか。その一言は胸のうちに仕舞って、堀川さんに微笑みを返した。
「いいえ。お礼なら、十分もらいましたから」
え、と堀川さんが訊き返す前に、木の陰から打刀の敵が躍り出てきた。なんとか攻撃を受け止めることはできたけれど、今度は随分数が多い。打刀からの二撃目を防ぐついでに、樹木の幹を足場にして敵の肩に飛び乗り、そのまま背後をとって素早く斬りつけた。続けざまに短刀に狙いをつけて刀を逆手に構え――ようとしたところで、遠くから堀川さんが叫ぶ声が聞こえた。
「危ない!」
その瞬間、視界が真っ白になって、斬撃の音が響いたきり、何も聞こえなくなった。身体も自分の意思で動かせなくなって、何かに吸い寄せられるように意識が遠ざかってゆく。
ああ、ボクは勝利を運べなかったのかな――。その心残りを最後に、いよいよ完全に思考が途切れた。
*
次に目が覚めた時には、本丸の手入れ部屋にいた。気がつきましたか、と主様の声がする。主様は、任務が無事成功して、本丸の歴史が守られたことを教えてくださった。
身体を起こして、成功してよかったです、と胸を撫で下ろした。出陣先での出来事を頭の中で反芻して、きちんと覚えていることを確かめる。そうしているうちに、ふと主様と視線が合った。主様のお顔を見た瞬間、器から水が溢れるみたいに堀川さんの言葉が一気に耳の奥に蘇って、胸の辺りがあつくなった。
「あれ……」
不思議なことに、だんだん視界が滲んで、目のふちから水が零れてきた。戸惑いながらそれを手の甲で受け止めていると、主様は驚いて、どこか痛むのでは、と心配してくれた。違うんです、と慌てて首を振ったけれど、主様は、出陣先で何かあったのか、いつものようにモニターできればよかったのに、とすごく真剣に考え込み始めてしまった。
目をぱちくりさせてその様子を見ているうちに、いつの間にか顔が綻んだ。主様は、ボクが密かに笑っている理由が分からない、という表情で瞬きをした。ボクは涙を拭い、いっぱいの敬愛を込めて主様に笑いかけた。
「主様。主様が話したくなった時で構いません。いつか、妹君と従妹君のお話、ボクにも聞かせてくださいね」
手入れ部屋を出られたのは、もう夕方に近い時分だった。下駄を持ってきて、縁側から中庭に下り、早春の空を見上げてみる。そうしたら、南の空高くに白い半月を見つけた。夜空に輝くのとは違って、縹色の空のなかにひっそりと静かに浮かぶ、真昼の月。
目を細めて笑いかけてみたら、月が微笑み返してくれた気がした。
この道
二月十九日。書類に筆を走らせていると、珍しい男士が執務室を訪れた。
「主、ちょっといいかな」
わたしは一旦手を止めて彼を執務室に招き入れた。談話室ではなくわざわざここに来るということは、何か用事があるのだろう。「どうしましたか」と話を促すと、髭切は、思い出したことがあったんだ、と切り出した。
「例の、僕たちの初めての出陣の時のことなんだけどね。怪我を負って物陰に隠れている間、小さい頃の彼女としばらく話をしていたんだ」
わたしたちの子ども時代である平成時代に出陣させた時の話だ、とすぐに思い当たる。すなわち、髭切の言う「彼女」とは、わたしの従妹のことだ。
「それで、彼女、今思えば少し気になることを言っていたなと思ってね」
気になること? わたしがそう繰り返すと、何か思案している風だった髭切は、あらためてわたしと目を合わせて言った。
「うん。……『あのこわいの、まえにもみた』、って」
*
二月二十二日。このところは、新しく本丸に顕現した刀剣男士を中心とした部隊が組まれ、ずっと戦国時代の京都に出陣している。各刀剣男士間の練度差は極力少なくなるように采配されているし、俺たちの方も検非違使の対処にだいぶ慣れてきた。
俺は今日の近侍として、主の横で胡坐をかいて座り込み、鏡を覗き込んで戦況を見守っていた。今日も敵の本陣まで危なげなく進軍し、隊長の小狐丸が主の指示を聞いて小さく頷いている。部隊は極力目立たぬように市街地を避けて移動していたが、偶々山間の集落に行き当たったらしい。民家の裏で赤子をあやしながら洗濯をする女の姿が、モニター用の鏡越しでも遠目で確認できた。やがて赤子がぐずり出し、たちまち甲高い泣き声を上げ始めた。そこまでだったら、特に気に掛けるまでもない、取るに足らぬ一幕だと言えるだろう。だが、赤子の泣き声が鏡の中から聞こえた瞬間、隣にいる五鈴が身を固くして小さく息を呑んだのが分かった。どうした、と尋ねるより前に、小狐丸がのんびりした調子で、主にとも部隊員にともなく独りごちた。
「おや、起こしてしまいましたか。赤子は人ならざるモノの気配を鋭く感じ取ると言いますからね」
主は小狐丸の言に相槌を打つでもなく、白い指を口許に当てて、鏡の中の様子をただただ見つめていた。顔色が悪い、と言うほどでもないが、何か動揺していることは明らかだった。
「……ぬしさま?」
小狐丸も審神者の様子が普段と違うことに気付いたらしい。「じきに本陣に到着しますが」と、様子を案じるように指示を仰いだ。
「きみ……」
俺が横から口を挟もうとするのを遮るように、五鈴は首を横に振った。
「いえ。――問題ありません。小狐丸、引き続き進軍を」
それからの主は、まったく普段通りだった。ただ、六振りが無事に敵を下し、自陣に大きな怪我も無いと分かると、緊張の糸が切れたように静かにひとつ息をついたのが印象的だった。
鴬張りの廊下が、ふたり分の足音で小さく鳴った。部隊の帰還を待つ間に、南側の正門まで行って出迎えの準備をする必要がある。その道すがら、ふと彼女に尋ねてみた。
「赤子の泣き声は苦手か?」
五鈴はこちらを見上げて一瞬目を瞠ったが、すぐに首を振って微笑んだ。
「いえ、そんなことは。うちの神社にも、赤ん坊や子どもを連れた参拝者は大勢来ますし」
幼子とのふれあいを思い出したのか、五鈴の表情はやっと柔らかくなった。
「心配をかけましたね。何かあったというわけではないのです、本当に」
俺は、そうか、と頷いて、それきりその話を打ち切った。そこから正門に着くまでの間、何度か主の横顔を窺うと、いつの間にか目を伏せて、指の関節を唇の下に充てる仕草をしていた。それが何を意味するか、一年以上にわたる付き合いの中で俺は学んでいた。彼女が何かを考え込む時の癖だ。
*
二月二十五日。資材の点検を終えて倉庫から母屋に戻る途中で三日月宗近と一緒になった。天気が良いので庭を散歩していたそうだ。
道中、溜め池の横を通ると、鯉の鱗が陽光を反射してきらきらしていたのが見えたので、ふたりでしゃがみ込んでしばらくそれを観察することにした。楽しそうに鯉を眺めていた三日月は、ふとわたしを振り向き、世間話でもするように話しかけた。
「どうだ、主よ。近頃は、少し元気が無いように見えるが」
一瞬、呼気が喉に詰まった気がした。そう見えますか、と返すのが精一杯だった。
「小狐丸か鶴丸から、何か?」
「いいや、夕餉で顔を合わせた時の様子を見て、何となくな」
三日月は、思い過ごしであればそれでよい、と付け足してくれた。
わたしは袴の上に置いた両手に視線を落としたまましばらく沈黙した。鯉の尾が水を弾く音だけが耳に残る。それを四回か五回聞いた頃、わたしはやっと顔を上げる気になって三日月の目を見返した。彼のまばたきに合わせて、打ち除けの月が白く輝いた。それを見た瞬間、あの雨の日に彼と話した内容を昨日のことのように思い出した。
わたしは立ち上がり、自室で詳しく話をする旨を伝えて、母屋の方に三日月を促した。
三日月を座布団に座らせて話を始める前に、同席させたい者があとひとりいる、と三日月にことわった。かくして招集に応じた鶴丸国永は、戸惑うでもなく自然に座布団に胡坐をかいた。対面に座るふたりとそれぞれ一度ずつ目が合ったことを確認してから、わたしは一度唇をしめした。
「鶴丸は隣に控えてもらっていたので、承知しているかと思いますが。先日の出陣の時――」
数日前に出陣をモニターしていた時の出来事をかいつまんで話すと、鶴丸はいつになく真剣な表情で頷き、三日月は考え込むように睫毛を伏せた。
「ふむ。赤子の泣き声か」
わたしは頷き、あの子どもの声に自分自身の記憶が重なったことを説明した。
「十五年ほど前の記憶です。あの子が、脚に怪我を負った時の」
それを聞いて、鶴丸が腑に落ちたとでも言いたそうに「そうか」と小さく呟いた。
「ふたりは、その時の詳しい様子を聞いたことは?」
「無いな。本人からも、二の姫からも」
ふたりの答えは大体同じだった。わたしはしばらく躊躇ったが、やはりこの懸念は共有するべきだと肚を決めて話し始めた。
「彼女が、まだ二つか三つの頃――」
わたしはやっと学校に上がるか上がらないかの時分だった。その日のことをそれほど事細かに覚えているわけではないが、後に両親や叔母夫婦から聞いた話によると、事の経緯はこうだった。
「母親と手を繋いで歩いていた時に、急に何かにつまづいて転んだらしいのです。母親は、当時生まれて間もなかった史弦がちょうど泣き出したので、そちらに気をとられたと。その一瞬のことだったそうです。転んだ彼女の傷はさほど深いようには見えなかったそうですが、すぐに応急処置をして病院で治療を施しても、なぜか異様に治りが遅くて」
その傷が完全に治ることはついぞ無かった――わたしはそう話を結んだ。
「まさか、それが……」
三日月はそこで言葉にするのをやめたが、わたしも鶴丸も、三日月の意図をすぐに了解した。
「可能性は、あります。あの時の、髭切たちの報告を考え合わせると」
「つまり、時間遡行軍と偶然接触しちまった、と。かなり小型の短刀の尻尾につまづいたってとこか」
「その時代の近辺に、歴史改竄の痕跡はあるか?」
三日月がこんのすけに訊いた。こんのすけは狐の手で器用に端末を操作して、モニターを見ながら首を傾げた。
「ええと……うーん、条件に合致する記録は見つかりませんね。それでは、時代と場所の検索範囲を少し広げてみましょうか。……だめです、今度は数が多すぎます。特定はかなり難しいかと」
そうか、と三者三様の溜息をつく。鶴丸が思いついたように言った。
「なあ。つまづいて足を怪我したってことは、遡行軍はほとんど地面すれすれに居たって考えられるよな?」
「そもそも、三の姫の霊力が高いとはいえ――いいや、むしろ霊力が高いからこそ、時間遡行軍の禍々しい穢れの影響を強く受けるはずだ。例えわずかな接触であっても、怪我だけで済むとは思えないがな」
三日月の言はもっともだった。大人のわたしでも、昨年襲撃を受けた時、時間遡行軍が近くにいただけでかなりの負荷を感じた。それなのに、わたしよりも霊力の高いあの子が子ども時代に時間遡行軍と直に接触して、命に別条が無かったというのはどういうことだろう。考えられるとしたら……
「……弱っていた?」
わたしの呟きに、鶴丸が小さく息を呑んで膝を打った。
「そうか。遡行軍のその個体が、かなり衰弱していたとしたら。それこそ、道端に落っこちて動けなくなるくらいにな」
それなら、穢れに触れても命までは蝕まれなかったことも頷ける。
「どこぞの戦で打ち漏らされた残党が、偶然平成時代のこの町に落ち延び、力尽きた」
モニター上の地図を指でなぞりながら三日月が言う。わたしがその先を引き取った。
「そして、その残党が事切れて身体が崩れる前に、あの子が通りかかって接触してしまった。……あくまで、仮説ですが」
「ああ。確かに、そう考えると辻褄は合う。だが……」
鶴丸は苦い顔をしてこんのすけを見た。管狐は耳を伏せて困ったように言った。
「そうですね。先日の件と違って、明確にその人間が狙われて攻撃を受けたという証が無い限り、出陣許可を得ることは難しいと思います。その時間遡行軍が刀剣男士に斬られたという記録は残っていても、命からがら逃げ延びた残党がどこでどう消滅したかまでを追うことはできませんから」
そこまで言った時、ちょうどモニターが入電表示に切り替わった。こんのすけ宛てのようだ。こんのすけは耳をぴんと立てて「ちょっと失礼します」と短く言うと、前脚で襖を開けて室を出て行ってしまった。それを見送って、室内はひととき静寂に包まれた。やがて、三日月がどこにともなく呟いた。
「とはいえ、方法は……無くもないか」
「ああ。本気でそれを阻止しようと思ったら、出来なくはないと思うぜ」
鶴丸は、特にわたしを唆す風でもなく、あくまで淡々と説明した。
「どこか手近な時代に出陣して、『短刀を一体逃した。深手を負わせたので放置しても問題ないと思うが、念のため追跡して、自分たちの手で始末をつけたい』とでもでっち上げればいい。あとは、また平成時代に出陣して、短刀が三の姫と接触する前に仕留めてしまえばおしまいだ」
そうすれば、幼い頃のあの子が怪我をすることもなく、あの日、ふたりとも火の手から逃げられたかもしれない。彼女たちの未来を取り戻すことができるかもしれない。ただし、歴史の修正力が働き、結局どこかで辻褄合わせが行われる可能性もある。いや、歴史上の重要人物であればともかく、こんな只のいち審神者の周りで起こった事象に対して修正力が働くのかどうかは疑問だが。ともかく、一度歴史に介入してしまえば、その後、ことがどう運ぶのかは誰にも分からない。それだけは確かだった。
わたしは顔を上げた。鶴丸がまっすぐわたしを見つめて言った。
「どうする? 決めるのは、きみだ。“大将”」
わたしは言葉に詰まり、三日月の方を見た。わたしを見る三日月の目は、どことなく憂いを含んだ色をしていた。それが意味するのは、憂慮か、悲観か。思考の海の底に沈んでしまう前に、わたしはひとつ息をついて、ふたりに向かって頷いた。
「……ええ。即答はできませんが、しばらく考えます」
*
二月二十六日。
寝む前に厨に立ち寄り、その帰りに屋敷の南側の回廊を通った時、ひとりの刀剣男士が片膝を立てて夜空を仰いでいるのを見つけた。山姥切国広だ。わたしは彼の隣に立ち、挨拶の代わりにこう話しかけた。
「よく、ここで星を見ていますね」
山姥切はわたしを見とめ、白い布の向こうで「ああ」と首肯した。
「刀だった頃にはその発想すら無かったが、不思議なものだ」
でも、彼が顕現したばかりの頃は、不寝番の時も読書をするか本体の調整をするかで、こうして星を眺めることは少なかったような……。そこまで考えた時、急に合点が行った。妹が話していたことが脳裏に蘇ったのだ。
ふと息を漏らしたわたしを見咎め、山姥切は俯いて布を深く被り直す。
「可笑しいか。俺なんかが人間の真似事をするのは」
わたしは反省して首を振り、座り込んで彼と目線を合わせた。
「いいえ。嬉しいのです」
山姥切は、どういうことだ、という目をしてわたしの方を見た。わたしは重ねて言った。
「昨年の九月頃だったか……あやめが言っていました。近頃、星空を見上げるのが楽しみだ、と」
短く息を呑む音がして、湖のような瞳が一瞬揺れた。
「寒くなるに連れて空気が冴えて星もよく見えるようになるので、当時は、そのことを言っているのかと思ったのですが」
どうやら違ったようですね、とわたしが微笑むと、山姥切は一瞬視線を彷徨わせ、結局はまた俯いてしまった。
わたしは軒下から空を仰いだ。散りばめられた無数の星が瞬く音が聞こえてきそうな夜空だった。――あの星のように光る欠片が、きっと彼の中に残っているのだろう。あの子の記憶という名の欠片が。それは、あの子の存在が既に彼の物語の一部になったことを意味しているように思えた。
わたしはもう一度山姥切の名を呼び、今だけは審神者としてではなく、彼女の姉として話しかけた。
「あの子によくしてくれてありがとう」
彼は相変わらず俯いたまま、それでも一呼吸置いて頷いてくれた。それを見届けてから、わたしは就寝の挨拶をして、自室に続く部屋の襖を閉じた。
*
何を考えているのか分からない人間だと思った。ずっとそうだった。もっとも、向こうのほうでも自分に対してそう思っていたかもしれないが。ただ、戦局判断については信用できる君主だと思った。
主はあれ以来、妹姫たちについて深く語ることはなかった。筆を滑らせる手を止めて、執務室の窓からじっと外を眺め、物思いに耽っている時間は増えた気がするが、それだけだ、と言うこともできる。――どういうことを考えている人間なのか、知りたいと思った。
如月の二十八日、日曜。気温は低いが、ここ数日は厭になるほどの晴天続きだ。雲ひとつ見えない晴れの日は、あまり好きではない。特に、こんな風に明るすぎる昼下がりの時間帯は。
否応なく降り注いでくる陽の光に目を眇めながら回廊の角を曲がった時、柱に寄り掛かっている後ろ姿が見えた。勿論、浅葱の袴と背格好で判別できる。この本丸の主だ。
近付いて声を掛けようとしたが、眠っていることに気付いてやめた。転寝とは珍しい――と主の寝顔を見ていると、彼女の鼻筋が二の姫にも三の姫にも似ていることに気が付いた。血の繋がった親戚なのだから当然だ。――いや、俺は何を考えている? 本科山姥切と比較されることを散々倦んできた俺が、審神者に他者の面影を重ねるなど、可笑しなことを。
白い布を一段深く被って、彼女の肩に掛ける羽織物を探すために踵を返そうとした時、視界の端で、主のまなじりを水が一筋つたうのが見えた。俺は立ち止まって、彼女を揺り起こすべきかどうかを考えた。状況から考えて、起こした方が良い内容の夢を見ているんだろう。だが、覚めたくない夢の場合も――
主の肩のそばに手を伸ばして考えているうちに、結局主は自然に目を覚ました。そして、自身でも気付いたらしく、驚いたように涙の跡に手をやっていた。
ちょうど傍の菓子盆のところにあった、ちり紙の箱を彼女に差し出した。主は「ありがとう」とそれを受け取った。
ちり紙を几帳面に四角に畳んで涙の跡を拭うのを見ていると、不意にそうしたくなって、主の隣に座った。彼女は意外そうにこちらを見た。それはそうだ、とりたてて用事がある時以外に主の隣に座ったのは、顕現してから初めてかもしれない。
何の夢を見ていたのかを尋ねる気はなかった。その代わりに、梅の花が咲いた中庭の様子を黙って眺めた。やがて風が吹くと、梅の花弁が散り零れて、池の周りの丸石の上に静かに落ちた。
*
「近頃、ようやく店というものが分かってきた気がするな」
弥生の三日。万屋からの帰り道、三日月が独り言のように呟いた。一年以上頻繁に伴を頼んできたのに……と五鈴が三日月の長閑さに苦笑する。俺は、それでこそ三日月だなと思いながら灰色の空を仰いだ。今日は朝方雪がちらついていたが、これから天気は回復に向かいそうだ。
三名分の履き物が砂道を踏むと、足元に小さな土埃が立った。万屋から本丸へは、甘味屋の角を曲がって、それから仕立て屋の前の道を右に折れて、あとは道なりに歩いていれば辿り着く。頭の中に道順を思い描いている途中で俺はふと気付き、この先の道を指差してみた。
「この道、ここまで来たら、本丸まで一度も曲がり道が無いんだな。ほら、真っ直ぐだ」
細い脇道はいくつかあるものの、結局それらも行き止まりになるか、この大通りに合流するかのどちらかだ。五鈴は同意して、俺の指先を目で追った。そして暫く押し黙ったかと思うと、徐々に歩みを緩め、ついに完全に立ち止まってしまった。どうしたのかと振り返った俺たち二振りに、彼女は順に視線を配った。
「三日月、鶴丸。先日の話ですが」
その表情で、彼女が何のことを言っているのかすぐに察した。
「決めたか」
三日月の問いかけに、五鈴はひとつ頷きを返す。
「ええ」
何を、と俺が尋ねると、五鈴はその場で後ろを振り返った。
「あの子たちが紡いできた、これまでの道を慈しむことを」
俺と三日月も彼女の視線を追う。開けた視界の中に、霞んで見えないほど遠くまで続く真っ直ぐな道だけが伸びている。その遥か先を、五鈴は懐かしそうな目で眺めていた。風が吹いて、緩く結った彼女の髪が背中で揺れた。
三日月宗近と目を合わせて頷き合う。「そうか」と返事をすると、その言葉はたちまち白息となって早春の空気に融けていった。
前夜
二〇十八年、五月。二十六歳になって数日経った週末。
わたしは軽装に薄物を羽織って、縁側で月見をしていた。今宵は十三夜の月。あと数日で望月を迎える。
西の方の廊下から衣擦れの音が聞こえて、三日月宗近が現れた。目が合うと、彼は微笑んで「明日か」とわたしに話しかけた。
はい、と答えて、三日月を自分の隣に座るように促す。彼は今まで歌仙兼定と碁を打っていたそうだ。また非番の日にでも続きを打つ約束をしてきたそうで、現在の勝率は丁度五分ずつであることを楽しそうに教えてくれた。
二言三言、雲の掛かっていない今宵の月が美しいことや、明日の準備について言葉を交わした後、彼はわたしに今どんな気分かを尋ねた。わたしは口許に手を宛ててしばらく考え、一言ずつ確かめるように口に出した。
「……共に人生を歩いて行きたいと思える人ができて、明日、その人と一緒になるのだと思うと、不思議な心地です」
審神者会議の前後の時間に本丸運営や刀剣のデータについてやりとりを重ねる中で、個人的な付き合いを持つようになったのが約二年前。それから兄が結婚したのをきっかけに、わたしにも縁組を、という話が持ち上がったのが約一年前。
「懐かしいな。あれほど長い溜息を聞いたのは、このじじいも初めてだった」
「本当に、あの時ほど気が重かったことはありません」
婚約者を両親に紹介する時、お互いに馬が合わないかもしれない、という懸念は一切無かったけれど、父が“時の政府”をどう思っているかはよく分かっていたから、相手の職業を明かした時の反応だけが心配だった。実際、顔合わせの当日は、職業の話になると空気が重くなったのがはっきり感じられたものだ。けれど、それから時間をかけて婚約者とも親とも相談を重ね、結局はわたしが大椙姓から抜けるということで結婚が許された。
「婚約直後の頃、人妻になるのかと包丁藤四郎が目を輝かせて尋ねてきたこともありましたね……」
「一期一振が包丁の首の後ろを掴んで引きずっていった姿、今でも覚えているぞ。あの時の一期の機動は、修行後の短刀に勝るとも劣らず……」
思い出話に花を咲かせて一段落ついた頃、ふと会話が途切れて空白が生まれる。その時、「できれば、あの子たちにも報告したかった」という言葉が自然に口から零れた。三日月は懐かしそうに目を細め、それに同意してくれた。わたしはその微笑みに後押しされるように言葉を重ねる。
「――実を言うと、笑うことは、まだ怖いと思う時があります。なぜかと問われても、わたし自身も答えを持たないのだけれど」
三日月は「そうか」とだけ答え、わたしの視線を追って月を見上げた。
「そのままでよい。今は、明日をより佳き日にすることだけを考えることだ。そうやって日々を過ごしていけば、長い時のなかで変わるものもあり、癒されるものもあろう」
三日月の言葉は、たびたびわたしの意識を遠い過去や遠い未来にまで誘ってくれる。それは、わたしたち人間が空に浮かぶ月に思いを馳せる感覚と少し似ていると思った。
ひとつ息をつくと、小さな懸念も吐息と一緒に空気のなかへ消えてゆく。わたしは立ち上がって寝室の方に足を向けた。この夜が明ければ訪れる明日のために。
「ありがとう。……おやすみなさい」
*
五月二十八日。神社での挙式を終え、一旦わたしだけ本丸に戻ってきた。みなで記念撮影を行うためだ。写真機を操作する役目は、お手伝いできるのが嬉しいからと、物吉貞宗が引き受けてくれた。
打ち掛けの裾を持ってくれた平野と前田に礼を言ってから、歌仙に誘われるままに写真機の前に立つ。
「はい、皆さん、十数えたら撮影ですよー!」
物吉の合図で、正面の写真機のレンズを見つめる。すると、昨夜三日月に話したことが一瞬だけ頭を過ぎった。挙式は厳かな雰囲気だったし、周囲への挨拶であわただしくて何かを考える暇も無かったけれど、今この瞬間、自分がどんな顔をしているかが急に気になった。心拍数が上がる。誰かに話しかけようかとも思ったが、もう写真機のタイマーが押されるところだ。
その時、風が吹いて、中庭の木々の若葉を揺らした。そのさざめきに混じって、二人分の声が確かに耳を撫でていった。
『姉様、笑って!』
反射的に背後を振り返る。そこには当然、見慣れた中庭の風景だけがあり、陽光を透かした若葉と地面に出来た斑模様の影が風に揺れているばかりだった。みなの様子を窺うに、わたしと同じように彼女たちの声が聞こえた者は他にいないようだ。
わたしは心の中で彼女たちに返事をしてから、写真機の方へ向き直った。視線の先には、物吉のあたたかい笑顔が待っていた。
「撮りまーす! 笑ってください、主様!」
莟
二〇一九年、四月六日。文机に向かってぼんやりカレンダーを眺めていると、廊下の向こう側から忙しい足音が近づいてきて、鈴を鳴らすのももどかしそうにわたしを呼んだ。
「五鈴さん。五鈴さん」
返事をして入室を許可すると、声の主――清光は障子を開けるなり、わたしのすぐ横に膝をついて座り込んだ。
「あのさ、体の具合どう? しんどくない?」
わたしがその勢いに圧されて何も返答できずにいると、清光は「あ、そうだよね、急だよね」と自己解決して、わたしのもとを訪ねてきたわけを話し始めた。
「最近、新しい刀も増えてないし、お客さんも無いし……主もどっちかっていうと体の調子良くはないって言ってたでしょ。出陣も無理のない範囲にしてるし。それなのに、さっき一緒におやつ休憩してた三日月が、『最近、何だか本丸が賑やかな気がするなあ』って。なんかちょっと嬉しそうに、笑顔でさ」
なるほど、と相槌を打ちながら彼の話を聞いているうちに、何となく話の筋が読めてきた。清光の声は、慌てるあまりに少しだけ震えている。
「俺、じーさん何言ってるんだろって思ってたんだけど、もしかして、もしかしたら……」
「…………」
わたしは返事の代わりに、彼と目を合わせて一つ瞬きをした。
*
翌日、四月七日。病院から本丸に戻ると、正門の前で清光が待っていた。彼が駆け寄ってきて「どうだった?」とわたしに問う。
「昨日、あなたが知らせてくれた通りでした。夫に連絡するために自宅に寄って、実家にも電話を入れてきたところです」
「そっかあ。五鈴さん、おめでと」
「ありがとう。こんなに初期に気付く人も珍しい、と医者に驚かれました」
清光はそうなんだ、と笑って、冷えるといけないからと首巻きを貸してくれた。そのまま玄関までの道を歩きながら、これからの本丸運営方針を少しずつ話した。遠征中の長谷部には少し報告が遅れてしまうが、歌仙には先に色々と相談しておきたいところだ。そう言うと、清光は打刀の寝室の並びを指差した。
「歌仙なら、今日は自分の部屋でお花生けてるって。まだ居ると思うから、話してくるといいよ」
歌仙の室を訪ねると、ちょうど作品が出来上がったらしく、見事な生け花が床の間に飾られるところだった。声を掛けて室に入ったところで、歌仙は手を止めてわたしを見上げた。
「ああ、君か。お帰り。大事はなかったかい。医者に診てもらってきたと聞いたけれど」
そこまで聞いているなら、もう突然話してしまっても問題ないだろう。わたしは歌仙の向かいに座り、早速本題に入ることにした。
「話というのは、そのことなのですが。わたしがこれからしばらく暇を貰うことになりそうなので、一定の準備期間ののち、この本丸を一旦休眠状態としたいと思……」
情報を伝える順番を誤った、と途中で気付いたがもう遅い。歌仙はたちまち血相を変えて膝立ちになり、わたしの両肩を掴んだ。
「そんなに悪かったのかい」
わたしは首を振り、肩に載せられた歌仙の右手に自分の右手を重ねて軽く握った。
「いえ、……産休と育休、と言って伝わるでしょうか。子を産み育てる期間のことです」
「そうか……。そうか! やあ、嬉しいな」
意味を理解するやいなや、歌仙の表情はみるみるうちにほころび、声にも柔らかさが増していった。だが、そこではたと我に返ったように動きを止め、居ずまいを正して再び座布団に腰を落ち着けた。
「……それで、しばらく本丸を空けるという話だったね。すまない、浮足立ってしまって」
わたしは微笑んで首を振った。
「連絡が取れる日もありますが、基本的には通信を利用して遠隔で指示をすることになると思います。本丸の休眠状態というのは……」
一番刀との話し合いは、昼餉の時間だと清光がわたしたちを呼びに来てくれるまで半刻ほど続いた。
*
次の水曜日。審神者会議があったので、ついでに本丸休眠の手続きを行うために政府の事務方のフロアに立ち寄った。すると、例の合同審神者会議でわたしに関する噂話をしていた審神者のうちの一人の姿を偶然見つけた。声をかけようとは思わなかったが、向こうも偶然わたしに気付いたようで、狭い廊下ですれ違いざまに目が合った。わたしは軽く目礼をしたが、あちらは何か部屋の隅に溜まった埃でも見るような一瞥をくれただけで、眉ひとつ動かさずにわたしの横を通り過ぎた。
ここ数年の間に審神者の霊力の平均値は目に見えて上昇し、今や、わたしのことをとくべつ能力の高い審神者だと噂する同僚は誰もいなくなっていた。もとより、わたしは時間遡行が解禁されたばかりの戦場をいち早く踏破できるわけでもなければ、新たに見つかった刀剣男士を常に最速で顕現させることができていたわけでもない。これまでの分不相応な評価が正常な方向に改められたというだけのことだ。
わたしはほっと息をつき、振り返ることなく、本丸休眠手続き用の窓口へと急いだ。合同審神者会議のたびにうっすらと感じていた息苦しさが、ようやく和らいだ気がした。
*
四月二十九日。今日からこの本丸は一時休眠状態に入る。休眠中は内番をしながら本丸で生活を続けても良いし、刀の姿に戻って倉庫で文字通り眠り続けても構わない――刀剣男士たちにはそう通達した。実際、しばらく戦に出られる見込みが無いならと、刀の姿に戻ることを選んだ者もいたが、長谷部は、わたしが戻って来た時にいち早く出迎えたいから、眠り続けるつもりはないと即座に答えてくれた。結局、少なくない数の刀剣男士が、休眠中も本丸での生活を続けることを選んだ。
この日、最後に本丸の正門まで見送ってくれたのも長谷部だった。正門の前まで辿り着くと、わたしは彼の方に手を伸ばし、お礼を言って風呂敷を受け取った。
正門から一歩出て振り返り、門の内側にいる長谷部と向き合う。すると、もう四年以上前、彼と出会ったばかりの頃のことが思い出された。正門ではなく屋内の廊下でだったけれど、あの時もこんな風に目を合わせた気がする。あの頃は、彼の目と態度が「自分をいくさで使ってほしい」「誰かに下賜しないでほしい、置いて行かないでほしい」と分かりやすく物語っていたものだが、今わたしを見る長谷部の目の奥には、その不安は欠片も見当たらない。
わたしは長谷部との距離を一歩分詰め、片方の腕を彼の背に回した。そのまま背中を二・三度軽く叩く。
「また、必ず共に戦いましょう。それまで、この本丸を頼みます」
彼も、わたしの身体を丸ごと支えるように優しく腕を回してくれた。
「ええ。お任せください」
耳元で聞こえた声には、もう自分が置いて行かれることはないという揺るぎない信頼が籠もっている。その思いを受け取って、わたしは現世へのゲートをくぐった。
*
二〇二〇年、三月。まだ完全復帰ではないものの、挨拶のために久しぶりに本丸に立ち寄った。
長谷部は宣言通り真っ先に出迎えてくれたし、みな息災で暮らしているようで何よりだった。自室で赤子の世話をしていると、赤ちゃんを見てもいいですか、と短刀たちが遠慮がちに話しかけてきた。それを了承して短刀たちを部屋に入れたところで、玄関の戸が開く音がした。
「主さん、お帰りー!」
一言聞いただけで分かる。鯰尾の声だ。骨喰と共に万屋に行っていたらしい彼は、ただいまの代わりにそう言って、次いでバタバタと手洗い場に直行した。「兄弟。赤ん坊たちが眠っているかもしれない」という骨喰の冷静な声が後を追った。
幸い、娘たちは前田と秋田に抱っこしてもらって、平穏な表情で眠っていた。その寝顔を、毛利藤四郎がひときわ目を輝かせて見つめている。
鯰尾たちよりも先に、三日月と石切丸が室を訪ねてきた。挨拶と娘たちの紹介をした後、わたしは一旦席を立った。廊下に出ると、すぐに鯰尾と落ち合えた。
襖をそっと開けて、鯰尾を室内へと促す。娘たちはわたしが離席している間に目を覚ましたようで、男士たちにあやしてもらって機嫌よく笑い声を立てていた。わたしは娘たちを膝に抱っこして、はじめまして、と彼女らの顔を鯰尾の方に向けた。娘たちは瞬きを繰り返し、初めて見る鯰尾のことを不思議そうに見つめている。
彼女たちと顔を合わせた瞬間、鯰尾は目を丸くして、わたしに向かって呟いた。
「五鈴さん……」
わたしには鯰尾が言いたいことがよく分かった。出産後に初めて娘たちの顔を見た時に、同じことを思ったからだ。二人とも、鼻筋の形はわたしに、口元は夫に似たようだが、目元は夫ともわたしとも微妙に違った。先に生まれた子の方は、わたしの母に似たまるい瞳。後に生まれた子は、おっとりした穏やかな瞳。
「葵と、美春と言います」
二人の名を順に紹介すると、鯰尾は「そっか……」と感慨深げに微笑んだ。そして、二人の手元に向かってそーっと右手を差し出した。
「よろしくね」
赤ん坊たちは小さな手で無邪気に鯰尾の指先を握り、楽しそうに笑っている。
夕七つの鐘が聞こえたら、娘たちの今日何回目かの食事の時間だ。わたしが調乳器具の準備をしていると、手伝っても良いかと三日月が手を挙げてくれた。
彼と連れ立って厨に向かう途中、わたしは自分に対して約束するような気持ちで言った。
「……当然ですが、あやめやみかせと娘たちを重ねるように接するつもりはありません。それぞれ別々の人間ですから」
けれど、名前の一音に希望を込めるくらいのことは、神様も許容してくださるだろうか。独り言のように最後にそう呟くと、三日月は目を細めて同意してくれた。
縁側の方で春告げ鳥が一声鳴いたので、そちらに目を移してみた。いつの間にか季節は一巡し、中庭はすっかり早春の様相だった。まだ肌寒い風のなかで、薄紅色の花の莟が今にも綻びそうにふくらんでいるのが見えた。
或る日
二〇二二年、三月二十九日。大侵寇がこれ以上激しくなる前にと、葵と美春を実家に預けるために本丸を出ようとしたところで異変に気付いた。本丸の周囲が黒い海のように消滅し、外に出られなくなっている。
一足遅かった。美春を抱いたまま動きを止めたわたしに、数珠丸が「一旦屋敷へ引き返しましょう」と進言した。葵は彼の長い髪を引っ張ったり指に巻き付けたりして、何も知らずに手遊びをしている。わたしは苦いものを噛み締めながら、数珠丸を見上げて頷いた。
屋敷に戻ると、こんのすけが制御室の前で待っていて、わたしに政府からの架電の内容を報告した。大侵寇の拡大、防人作戦を展開――。今回は政府との連絡手段は繋がっているものの、先ほど正門の外でも見た通り、状況は芳しくないらしい。迷彩機能に綻びが生じたわたしの本丸だけを狙って一気呵成に敵が押し寄せてきた六年半前とは異なり、時の政府のコアシステム自体が狙われているとあって、長期戦になる予感がした。
夜になると、中庭から異常に大きい月が見えた。管狐を通じた自立プログラムにて本丸の機能を継続するとはこういうことなのだと直感で理解した。
ひとまず、厳戒態勢を取りつつも、今夜は交代で寝むことにした。葵を寝かしつけながら、心の中で使命感と不安の天秤が釣り合う地点を必死で探した。そうしているうちに、いつの間にか暗い眠りの世界へ落ちていった。
翌日は執務室に籠り、昼戦・夜戦・室内戦のいずれにも対応できる部隊編成を長谷部と共に策定した。その途中で休憩のために厨に向かうと、階段を下りたところで三日月宗近と行き合った。三日月は、何も謝ることはないのに、わたしの顔を見るなり「すまんな。野暮用だ」とだけ言い置いてどこかに出掛けてしまった。現状、この本丸は現世から切り離されているものの、万屋への経路には影響が無いようなので、万屋街のほうに出掛けたのだろうか。――それにしては、どこか悲しそうな目をしていたのが気になった。
彼が帰って来たら話を聞いてみようか。そう考えていた矢先、屋敷全体に警報音が鳴り響いた。アラート内容は――『本丸に急接近する敵の姿を捕捉』。
すぐに迎撃隊を組み、出陣ゲートを開いた。歌仙兼定を隊長とした、我が本丸の精鋭部隊だ。しかし、モニター用の鏡に映っていたのは信じがたい光景だった。敵に遅れをとるどころか、こちらの攻撃が全く通っていないように見えた。――このまま突破されたらどうなる? 隣室で昼寝をしている娘たちの顔が頭を過ぎった。
その時、鋼の高い音がして、わたしの意識を戦場に引き戻した。三日月宗近が敵の攻撃を防いだ音だった。三日月は歌仙たちに何事かを一言二言告げて、そして――それきり姿を消した。
夜になっても、三日月は帰ってこなかった。屋敷の周囲には、透き通った大きな月のオブジェだけがぽっかりと浮かんだ、静謐な青い空間が広がっていた。
政府から何度目かの通達があった。敵の侵入を許さぬよう防衛ラインを築いたので、前衛・中央・後衛に分かれて各本丸総出で迎え撃てということらしい。わたしの本丸は前衛に配属され、押し寄せる敵を殲滅ないしは弱体化させる役割を付与された。
それから約十日の間に、三度にわたる大きな侵寇があった。その間に三日月宗近が姿を見せることはなかった。そして、更に数日の後。掃討戦を経て敵を完全に撃退したかと思われた時、椿寺に敵が総攻撃を仕掛けているという情報が入った。
「……主、僕が行こう。行かせてほしい。必ずふたりで共に帰るよ」
その言葉通り、一番刀の歌仙兼定は単騎で椿寺に出陣し、三日月宗近を見事に連れ戻してきた。
結果から言うと、三日月が黙って姿を消した理由をわたしはすっかり理解したが、この日記には多くを書き記さないほうが良いだろう。ただ、「何でもひとりで抱え込まず、相談するように」という彼からの七年前の忠告を、そっくりそのまま彼に返すことになったことは言うまでもない。
本丸が元に戻った夜、三日月はひとりで縁側に腰掛けて、平穏な中庭の風景を愛おしそうに眺めていた。わたしは黙って隣に腰掛け、同じようにした。中庭で咲き誇る春の花の匂いが夜風に混じっていた。
「……いつから? と聞くのは、無粋なのでしょうね」
三日月はこちらを振り向き、寂しげな困り笑いを浮かべて、是とも否ともつかぬ曖昧な答えを寄越した。
わたしたちが小声で雑談をしている最中、背後の襖が音を立てたので振り返ってみると、葵が器用に襖を開けてこちらに歩いて来るところだった。奥の部屋で寝かせていたのだが、いつの間にか目を覚ましたらしい。美春もたどたどしい足取りで一生懸命に葵を追いかけてきた。わたしは美春を回収して抱き上げた。好奇心の強い葵は早々と縁側まで辿り着き、そのまま三日月の膝に上って、紺青色の衣の裾を引っ張っていた。
三日月は優しく葵の手を取り、彼女の頭を撫でた。しばらくその様子を見ていたわたしは、やがて三日月の手の甲に何かが一粒零れ落ちたことに気付いた。涙を一杯に溜めた三日月の目を、葵が「どうしたの」とでも言いたそうに見上げ、もう片方の手を彼のほうに伸ばして、なだめるような仕草をした。
わたしは三日月の背に掌を添えてゆっくり撫でた。言葉という形で伝えられなくとも、彼がたったひとつだけ願い、幾度も夢見たものがこの瞬間なのだと言われたような気がした。
「守ってくれてありがとう。あなたが帰ってきてくれて、本当によかった」
夜が更ければ、やがて明日が来る。昨日と同じようで全く違う明日が。皆が此処に居てくれるという確信があるから、わたしは明日に進むことができる。そして、二度と戻らぬ、たくさんの『或る日』を刀剣男士とともに重ねてゆくのだ。
桃源郷は遥か
その刀剣男士がわたしたちの本丸へやって来たのは、夏の終わりの夕暮れ時のことだった。二〇一七年、八月二十五日。嫋やかな身のこなしで鍛刀場に降り立った彼は、千子村正と名乗った。
「初めまして、審神者さん。ワタシは、そう……妖刀とか言われている、あの村正デス」
武人にしては細い指を優雅に唇の下に充て、嫣然とした含み笑いを漏らす。次いで、挨拶代わりに脱いでも良いかなどと突拍子も無いことを言い出したので、思わず「むしろ、もう一枚羽織っては?」という提案が口をついて出た。今日は確かに蒸し暑いけれど、この地方の夏は短く、じきに朝夕は肌寒くなるに違いないからだ。顕現間もない彼にそう説明すると、彼は夕日を映したような瞳を丸くした後、上品な仕草で何やら楽しそうに笑い始めた。
ともかく、その風変わりな刀剣男士は、そんな風にこの本丸の一員になった。
*
十月二十五日。縁側に面した部屋で書き物をしていた時、廊下の方から光忠と村正が話している声が聞こえた。
「着物が土まみれになってしまいました。これはもう脱ぐしかないと思いませんか?」
「今ここで脱がなくてもいいんだけど……確かに、ご飯の支度をする前に汚れは落としておきたいよね」
今日の畑当番が終わったようだ。障子を開けて声を掛けようかと思ったけれど、ふたりの声はすぐに湯殿の方に遠ざかって行ってしまった。わたしはまた筆をとって報告書の作業に戻ることにした。
千子村正は、このふた月の間に出陣や内番を経験するなかで、他の刀剣男士との会話がだいぶ増えたようだ。同じ部隊に編成された仲間に、脱ぎ合おうと話しかけている場面を何度か目にした。なお、その勧誘の内容が良いことかそうでないのかは、誘われた側の男士の性格に拠るだろうから、ここでは言及しないこととする。
でも、とわたしは一旦筆を止めた。彼は一見社交的に振る舞っているようだけれど、その実、他者との深い交流は意識的に避けているように見えた。……身に覚えがある。審神者一年目の頃のわたしも、交流を避けていたというほどではないにせよ、心の奥深くの本音をきちんと打ち明けられるようになるまでには長い時間がかかった。そうだ、何故か彼の様子が気にかかるのは、個性的な振る舞いをする刀だからという理由だけでなく、どこか過去の自分の姿が重なるからかもしれなかった。
そういえば、顕現日に本丸を案内して以来、村正とは一対一で話す機会が少なかったし、気のせいか、向こうから近付いてくることも少ない気がする。練度を上げるために頻繁に出陣させているから、仕事上の関わりはむしろ多いはずなのに。
そう考えながら、手元の予定表に目を落とした。金曜日の部隊会議の出席者欄には、千子村正の名が記されている。
*
十月の二十七日、晴れ。
夕餉の後、審神者の五鈴さんに呼ばれて本丸の真ん中の制御室に行くと、もう大倶利伽羅と千子村正が座っていた。僕が座布団に座ると、来週の出陣に関する会議が始まった。
「さて。来週は、打刀六振りの編成で主に戦国時代へ……」
この間の戦力拡充計画で竹藪対策のために打刀六振り編成を試した時の名残で、最近は打刀中心の編成が多くなっている。僕たちは文机に広げた合戦場の地図を囲んで、一人と三振りで顔を突き合わせていた。
「ここで、酉の方角へ……。この動き、安定はどう思いますか?」
「そうだなぁ。ここはどっちも身を隠しやすい地形だから、攪乱目的で二手に分かれちゃってもいいかも。三振りずつか、四振りと二振りの分け方が良いかな」
僕は説明しながら、地図の分かれ道のところを指で示した。「どうかな?」と皆に聞くために顔を上げたら、文机の向こう側にいる五鈴さんと千子村正が、たまたま全く同じ表情・同じ姿勢で指の甲を唇の下に充てていた。髪型と元の顔立ちもあいまって、ちょっと座高が違うだけのそっくりな人間がふたり並んでいるみたいだ。……と思ってふたりを見ていると、隣でふっと息の漏れる音が聞こえた。あ、大倶利伽羅も気付いたみたい。僕もたまに無意識で加州清光と同じような仕草してることとかあるけどさ、指の角度までこんなにきれいに一致するのはやっぱり珍しいよね。分かる。
そう思っているうちに長考が終わったらしく、目の前のふたりは息を合わせたみたいに「では、こちらに……」と全く同じことを言って、地図の中の同じ箇所を指差した。さすがにそこでふたりとも気付いたようで、おや、という感じでお互いに顔を見合わせていた。
「ねえ、気付いてた? さっきもお揃いみたいな仕草してたよ。ふたり、ときどき似てる時あるよね」
僕はふたりに向かってそう話しかけて、最後に「あ、村正が真面目な話してる時限定だけど」と付け足した。それを聞いた五鈴さんがちょっと笑って村正と目を合わせようとしたら、村正は五鈴さんを一瞬見た後、ふいと気まずそうに顔ごと逸らしてしまった。
「安定サン、いいんデスか? ご神職であられる清らかな審神者様と、ワタシのような妖刀を似ているだなんて。罰が当たるかもしれませんよ」
ただの軽口のような口調だった。そんなことはない、と五鈴さんが首を振るのと、「罰なんて当たらないよ」と僕が言ったのはほぼ同時だった。そのあと、話の流れは自然に戦略の方に戻り、作戦の内容は無事にまとまった。つまり、いつも通りの日常の一幕だったんだけど、ただ、村正が言ったことに対して五鈴さんがすごく驚いた顔をしていたことだけが、部屋を出てからも何となく気になっていた。
*
十一月三日。今日は万屋へ買い出しに出掛けた。買うべきものが多かったので、近侍の長谷部に加えて、非番だった安定と村正にも同行を頼んだ。
万屋とわたしの本丸とのちょうど中間地点には、地元では有名な寺院がある。帰り道にその傍を通った時、何やら多くの人が集まっているのが見えた。大きな法要が行われているようだ。立て看板の一部が人影で隠されていたが、第五十回記念法要という文字がかろうじて読み取れた。
「大きな催しみたいだね」
そのようです、と安定と話していると、僧侶のかたの合図の声が聞こえて、空中に引かれた紐に吊り下がった白い器が貝のように二つに開き、色紙でつくった小さな散華が大量に舞い落ちてきた。
「わあ……」
安定が最初に感嘆の声を上げて空を仰いだ。散華は色とりどりの花弁のように、陽の光に当たって時折輝きながら、秋の高い空のなかを舞い踊った。
わたしたちは自然に足を止め、散華が風に乗って舞うさまをしばらく鑑賞した。「美しいですね」と感想をめいめい言い合うなかで、千子村正は独り言のように呟いた。
「この世の景色とも思えぬ……さながら桃源郷デスね」
桃源郷――中国の古典に描かれた理想の世。確かにこの光景は夢まぼろしの世界にも見えるかもしれない。わたしはそう考えながら目を眇めた。
村正は幾分声を硬くして続ける。
「……デスが、夢は夢。ワタシたちがこの世に在る限り、そんな場所が見つかることは無いのでショウ」
まるで、花が散って地に落ちてしまうことを惜しむような、寂寥と諦観の混ざった声だった。そうなのかな、と安定がぼんやり応じたが、村正は安定の方を振り向きもせずにただただ空を見上げていた。村正の裳の先がたなびくのと同じ速さで散華の一片が風に流され、ついに音も立てずに地面に落ちた。やがて、わたしが声をかける前に、村正はひとつ息をついて本丸の方へ歩き始めた。
わたしは最後にもう一度振り返り、まだ散華の舞う寺院のほうを見遣った。わたしの隣で、長谷部もその光景を目に焼き付けるようにじっと遠くを見つめていた。
*
十一月四日。宗三左文字が修行から帰還した。夕餉には上品な味付けの煮魚が並んだ。宗三の好物を主が厨当番に頼んでくださったようだ。俺はお優しい主君に恵まれて本当に誇らしい。今までに何度も感じた歓びを今一度噛み締めた。
夕餉の後、縁側に座っている宗三左文字の後姿が目に入ったので、何となくそちらに寄って行って話しかけた。
「今日は満月か」
宗三は月を見上げたまま「そのようです」と答え、俺が座る場所を空けた。
「……主は、僕が修行を申し出たことを意外だと言っていたでしょうね? 自分でも、随分突然だったと思いますから」
軽い苦笑とともに宗三が言った。確かにそうだ。主も宗三から申し出があった時は驚かれたようだった。俺は何故修行を決意したのかを宗三に改めて尋ねた。すると、宗三は暫く考える素振りを見せ、何か思いついたように「そうですね……」と呟いた。
「あの人、ずっと僕たちを安土に送るのを避けていたでしょう」
「……ああ」
主はお優しい方だ。かの地に出陣させるのであれば、それは俺たちが自ら望んだ時に、というお考えだったのだろう。俺がそう言うと、本丸随一の捻くれ者も今夜ばかりは素直に肯定の意思を表明し、昔を懐かしむような声で続けた。
「それに、天下人の刀である僕を侍らせて自慢したいなどという欲も無いようでしたし。二の姫も三の姫も、僕のことを魔王の刀として扱うようなことはなかった。だから、そんなあの人たちの刀として、僕も向き合うべきものと向き合って強くならねばと思ったまでですよ」
聞いているうちに、いつも楽しそうに宗三に話しかけられていたあやめ様のご様子が思い出されて頬が緩んだ。そのまま自然に、昨日の出来事を話す気になった。満月のお蔭なのか、今宵は俺も幾分口が滑らかになっているようだ。
「昨日、主の伴を仰せつかって万屋に行ってきた。いや、俺は近侍なのだから伴をさせていただくのは当然なのだが」
「前置きは結構ですよ。あなた、いま僕に話したいことはそれではないでしょう」
「…………」
俺は一つ咳払いをして、本題に入ることにした。
「帰り道で、理想の世についての話になった時、俺は無意識にあの男の姿に思いを馳せてしまったのだ。あの男が、理想の世をどう考えるのかを知りたいと、一瞬でも考えてしまった」
「まあ、当然でしょうね。好むと好まざるとに関わらず、浅からぬ縁があった相手であることは事実ですから」
宗三の相槌は厭になるほど的を射ていた。そうだ、どれほど今代の主だけに尽くそうと心を砕いても、結局、あの男の影から完全に逃げることなど出来はしないのだ。ならば、と俺は顔を上げた。
「俺は、真意を知りたいと思う。天下を夢見たあの男が、何を考えていたのかを。主のために更に強くなるには、俺が自らそれを知って、受け入れることが必要なのだろう」
「その“真意”が、あなたの望むようなものではなくても?」
「構わん。知らぬまま過ごすよりはずっと良い」
そう言い切ると、隣で小さく息が漏れるような声が聞こえた。年中細い溜息をついているようなこの同僚の微笑を、久方ぶりに目にした気がする。
*
十二月一日。しんしんと雪の降りしきる午後、わたしは執務室に籠もって千子村正に書類の整理を手伝わせていた。近頃、神社の方の行事が多くて本丸に立ち寄る頻度が下がってしまったので、提出物が溜まっているのだ。
村正は指先で書類を摘まみ、軽く目を通して決裁が必要なものだけをこちらに手渡しながら、少々呆れたようにぼやいた。
「まったく……近侍のへし切長谷部が修行に旅立ったからといって、同じ刀種からワタシを抜擢するなんて、何を考えているのだか。神に仕えるお方が妖刀なんかを側に置いて、何か起こっても知りませんよ。どうせなら、そうデスね……物吉貞宗や、御神刀の太郎太刀を側に置いた方が、アナタにとってもよほど利があるでショウに」
「…………」
二重の意味で誤解を解きたかったが、口先だけで否定したところで、彼の考えが簡単に変わるとは思えない。わたしはしばらく考えた末、結局言葉にするのをやめて目を伏せた。この間からずっと、頭の片隅でこの答えを探している気がした。
ふと横を見ると、筆を洗うために水を張った器のなかに、空虚な目をした自分の姿が映っていることに気付いた。その器に細筆を浸して、そのまま円を書くように動かす。すると、筆先に残っていた墨が溶け出し、透明だった水はみるみるうちに薄灰色に濁った。
その様子を眺めているうちに、視線を感じて目を上げた。わたしにつられて、いつの間にか村正も器の中を覗き込んでいたようだ。物思いに沈みすぎてしまったかと反省し、わたしは気を取り直して決裁済の書類の枚数を数えた。それを綺麗に揃えて机の脇に置き、急須と菓子が載った盆の方を示す。
「さあ、だいぶ進みましたね。そろそろ休憩しましょうか」
今日の茶請けは、中に甘い餡が入った白い団子だ。菓子楊枝で半分に切って口に運んでいると、向かいに座った村正が珍しく目を丸くして団子を味わっていることに気付いた。
「それ、気に入りましたか?」
つい言及したくなって尋ねてみたところ、村正は団子を一旦飲み込んでしまってから素直に頷いた。
「わたしもこの店の団子が一等好きです。確か店舗の方では、この団子を使ったパフェも提供していたと妹が言っていて……」
そういえば、この甘味処は万屋への道の途中に店舗を構えていた気がする。それを思い出しながら、わたしは興味深そうな目をした村正に“パフェ”について軽く説明した。そのうち、話題は村正ら三振りを連れて万屋に買い出しに行った日のことに移った。
「あの日、寺院の散華の光景がとても綺麗でした」
「ええ。あなたが言ったように、まるで桃源郷のようで」
極彩色の散華のなかに佇む村正の後姿を思い出す、この世では桃源郷など見つからないのだろう――あの時そう呟いた声に、わたしは確かに諦念と寂寥を感じ取った。
「……村正。ひとつ訊いても?」
そう尋ねると、長い指を湯呑みに添えて睫毛を伏せていた彼は、わたしと目を合わせて頷いた。
「桃源郷という言葉から、あなたはどんな世界を想像しましたか」
村正は窓の向こうの雪景色に目を遣って黙り込んだ。答えを考えているというよりも、どう話すか、あるいは、そもそも話すか話さないかを考えているように見えた。
「……今は、言いたくありません」
彼は結局、湯呑みに目を落としてそれだけをぽつりと零した。そして、気持ちを切り替えようとするような声で「アナタはどう思いマスか」とわたしに尋ねた。
わたしも彼と同じように考え込んだ。桃源郷。叶いはしないが、そうあってほしかった理想の世。
「そうですね……わたしも、口にするのは難しいかもしれません。けれど、あなたにはきっといつか話します。少しずつ」
そう話すわたしのことをじっと観察していた村正は、納得しているのかいないのか、返事の代わりに湯呑みを両手に包んで焙じ茶をひとくち嚥下した。
窓の外では、音もなく雪が降り続いている。
*
十二月四日。普段通りの出陣だった。行き先は元禄時代の江戸。自分以外の部隊員は、山伏国広、鶯丸、千子村正、骨喰藤四郎、太鼓鐘貞宗。その他、特に記すべきことは無い、筈だった。
道中、小さな農村の傍を通った。人目は避けるようにしていたが、武士のような風体の者が珍しいのか、どこからか数人の子どもが駆けてきて、足元に纏わりついたり衣の裾を小さい手で引いたりした。やがて、子どもはうちに寄って行ってほしいと千子村正の手を引いて駆け出した。村正は困ったような視線をこちらに寄越したが、断る方が面倒だと思ったのか、諦めたように溜息をつき、少しだけならと約束して子どもらの家に立ち寄ることになった。
手を引かれて子どもらの家の前に着くと、一人の子どもが一旦家の中に戻り、この家の家宝だという短刀を抱えて出てきた。子どもは太鼓鐘に短刀を見せながら、誇らしげに笑っていた。遠目でも判別できる。あの銘は……。
隣にいた者の様子を窺おうとした時、気配を感じた。
「おっと。チビっ子達、下がりな!」
太鼓鐘が反射的に子どもらを背中に隠して刀を抜いた。自分を含めた他の五名も太鼓鐘と同じことをした。
「ばけものめ! ぼくもこの刀でたたかうんだ! おとうとといもうとをまもるんだ!」
家宝だという短刀を抱えていた子どもが、慣れぬ手つきでその刀を抜いて前に出た。やめろ、と叫んだが、その子どもは聞かなかった。腕ずくで止めようにも、敵に進行を阻害され、子どもの前まで辿り着かない。舌打ちをして、敵の鳩尾を鞘で強かに突く。そうしているうちに、絹を裂くような子どもの声が背後で聞こえた。振り向くと、子どもが尻餅をつき、脇差型の遡行軍に向かって震える手で短刀を突き付けているところだった。
猶予は無い。迷わず子どもの腕をこちらに引き寄せた。子どもの体が浮くのと、その拍子に短刀が子どもの手から離れるのと、脇差の攻撃によってその短刀に罅が入ったのは同時だった。
子どもらを安全な場所に隠してから確認してみると、血液と砂で汚れ、いびつに割れた短刀が虚しく地に転がっていた。隣で戦っていた者が、その光景を目にして短く息を呑む音が厭に鮮明に記憶された。
*
十二月四日。午後の出陣にて、千子村正が意識不明のまま仲間に抱えられて帰還した。システムの判定では、重傷寸前の中傷だった。出陣させたのは元禄時代の江戸。練度が足りなかったという可能性は無い。その合戦場には、検非違使に嗅ぎつけられるほど頻繁に出陣させてもいない。
手入れ部屋で村正に霊力を送りながら、わたしは頭の中で状況を整理しようと試みた。モニター用の鏡で視認できたのは、それまで落ち着いて敵を斬っていた村正が、ある瞬間から明らかに平常心を失い、敵に背後をとられて傷を負わされたところまでだ。彼が平静を失うきっかけになった事象が何だったのかは、こちらからは窺い知れなかった。
そう考えているうちに、握った手に力が込められた。よかった、目を覚ましたようだ。名前を呼びかけてみると、彼の目が薄く開いてこちらを見たが、まだ意識が鮮明ではないらしく、どこか焦点が合っていないようだった。そんな中で、唇をしきりに動かして何か声を発そうとしている。怪我の痛みも相俟ってか、随分切実な様子だ。わたしに何かを伝えようとしている? わたしは耳を寄せて彼の言葉を聞き取ろうとした。
「ひと、ふり……折れ……」
「え……?」
わたしは思わず訊き返したが、彼はその一言を伝えるだけで限界だったようで、またすぐに深い眠りの海に戻って行ってしまった。わたしが寝床の脇に控えているこんのすけの方を振り向くと、彼も困ったように首を振った。
「ええと……今日出陣したのは、太刀二振りに、打刀二振り、脇差と短刀が一振りずつですね。審神者様もご存知の通り、データベースには千子村正の中傷以外の情報はありません」
そうだ、現に他の五振りについては、手入れの必要が無い状態で無事帰還したことを確認している。となると、彼が言っている一振りというのは誰のことだろう? こんのすけと顔を見合わせてみても、答を持たない者同士では如何しようもない。わたしは村正の様子を見ておくようにこんのすけに頼んで、一時的に席を外すことにした。
手入れ部屋の襖を静かに閉めた時、部屋の前に大倶利伽羅が控えていることに気がついた。彼は普段、誰かの手入れが終わるのをこんな風に手入れ部屋のすぐ前で待つことは少ないのに、どうしたのだろう。わたしが声を掛けようとすると、報告したいことがある、と彼の方から口を開いた。
彼の話によると、こうだった。農村で村正の短刀を持っている子どもと偶然出会い、そこに敵が襲ってきた。そして、千子村正の目の前で、村正の短刀が――。
「千子村正の剣筋に違和感を覚えたのは、そのすぐ後だった」
「なるほど……」
声が出せなくなるほどの怪我を負いながら、村正がわたしに何とか一言でも報告したがっていた理由がようやく分かった。おそらく、村正が目の前で一振り折れたという事実だけが強烈に記憶され、動揺のために認識の混濁が起こったのだろう。何だか、目を覚ました瞬間に夢と現実の境が分からなくなる現象と似ていると思った。
わたしは大倶利伽羅に礼を言って自室に帰した。彼が廊下を歩いて行く後ろ姿を見送った後、ひとつ息をつき、手入れ部屋の襖に向かって立ち尽くす。目を上げてみると、手入れの残り時間を示す数字が規則的に点滅していた。
*
十二月七日。
「今日の相手はお前か。ある意味、新しい戦法を試すのにちょうどいい機会かもね」
「模擬戦とはいえ、今日は主が見てるからね。三割増しで頑張っちゃうよ」
今日の手合せ当番は加州清光と大和守安定だ。手合せ前の宣言通り、身内同士ならではの遠慮の無さで、互いに一歩も退かぬ紙一重の勝負が繰り広げられた。そこまで、と判定係の堀川の声が掛かった頃には、ふたりとも疲れすぎてしばらく立ち上がれなかったくらいだ。わたしは堀川と一緒にふたりに手を貸して、ついでに木刀を預かった。
後片付けが終わって道場を出る時、わたしは腕に抱えた二振りの木刀を見下ろしてみた。そういえば、わたしの本丸の場合、真剣本体はそれぞれの刀剣男士が管理しているから、審神者が真剣を手に取ったりまじまじと眺めたりする機会はそれほど多くない。それに改めて気付き、心の隅に小さな引っ掛かりを覚えた。
「主さーん、こっちの灯りも落としちゃって良いですよね?」
更に深く考え込みかけたところで、堀川の声が耳に入った。わたしは思考を打ち切って彼に呼応し、道場の東の渡り廊下の方に向かった。
その夜、机に部隊表を広げて、来週の部隊編成について考えた。大阪城地下に向かわせている第一部隊は据え置きで、第四部隊は遠征、あとは戦闘経験を積ませたい男士を練度別で第二・第三部隊に振り分けようか……。頭の中で構想がまとまりかけた時、端の方によけておいた木札のひとつが指の先に当たった。千子村正の札だ。わたしはそれを取り上げて天井の灯りに翳した。
村正の身体の傷は翌日にはすっかり癒えたものの、それと戦闘意欲の問題はやはり別のようだ。ここ数日は、本丸内の雑事をこなしながらぼんやり遠くを見ていることが多かった。
「普段の言動の裏の真意、桃源郷の例え話、……折れてしまった短刀」
気にかかることを声に出して並べてみても、ばらばらに散らばった欠片同士が一つに繋がるようで繋がらない。何か最も重要な一欠片だけが足りていないような感覚があった。わたしはしばらくそのまま手の中の木札を弄んだ後、霧を吹き飛ばすような気持ちで短く息をついて立ち上がった。
頭の中を考え事で一杯にしたまま、手を義務的に動かして湯浴みを済ませた。就寝の準備をして寝室に戻る途中、縁側にひとり分の人影を見つけた。大和守安定が立ったまま月見をしているようだ。声を掛けようとしたら、安定の方が先にわたしに気付いて手招きした。
「五鈴さん。月、きれいに出てるよ」
安定が指差す先を目で追うと、なるほど、雲ひとつ無い澄んだ夜空に明るい月が浮かんでいる。
「本当ですね」
今日は昼間は曇っていたけれど、夕方頃から晴れてきたようだ。こんなにくっきりと輝く月を見上げたのは随分久しぶりな気がした。
ふたりで並んでしばらく月を眺めていると、安定が世間話でも始めるような口調で言った。
「僕、こうやって月を見てると、沖田くんのことを思い出すんだ。時々ね」
返事が一拍遅れたが、わたしは相槌を打って安定の方を向き、彼の話を促した。
「この間、桃源郷の話が出た時に考えたんだ。僕にとって桃源郷みたいなところがあるとしたら、それは、沖田くんがいて、五鈴さんもいて、……僕のことを大切にしてくれる大好きな人たちと一緒にいられるところかな、って。
それでね。幕末の京都に出陣した時に、綺麗な月が出てたのを思い出したんだ。ちょうど今夜みたいに」
安定はそう言って、ぽっかり浮かぶ月をまた指差した。
「あ、他の刀剣男士ともよく話すんだけど、時間遡行をする時って、一瞬どの時代にいるか分からなくなる感覚があるんだ。目が覚めた時に、夢かうつつか分からなくなる、みたいな感じ」
わたしはなるほど、と頷いた。ちょうど数日前に、全く違う出来事について同じ例えをしたことを思い出す。
「だから、時代が違っても、居る場所が違っても、本当の意味での隔たりなんて無くて、あの月が全部繋げてくれている気がするんだ。そう考えるようにしたら、何だか心強い気がする」
なんてね、とはにかむように笑って、安定は話を結んだ。わたしも微笑んで頷き返す。安定の考えは、わたしにとっても救いになる気がした。刀剣男士の心をかたちづくるものは、畢竟、人との因果や縁であり、その点ではわたしたち人間と何も変わりはしないのだろう。
――そこに考えが及んだ時、雲が晴れて月が顔を出すように、心に閃いたことがあった。わたしは安定との月見を終えた後、まっすぐ寝室に戻るのをやめて、屋敷の奥の書庫へ足を向けた。
*
十二月九日。わたしは廊下に掲示してある当番表を眺めていた。昨夜遅くにやっと組み合わせが決まったのだ。手合せ当番の欄には――と札を確認しようとした時、わたしの隣に影が出来た。顔を上げると、大倶利伽羅が微動だにせず手合せ当番の欄を見つめているところだった。彼はしばらくそうした後、軽く鼻を鳴らして踵を返し、渡り廊下の方に歩いて行ってしまった。あの方角なら、きっと道場に向かったのだろう。
わたしはもう一度当番表に目を移した。手合せ当番の欄には、大倶利伽羅と千子村正の木札が掛かっている。
「……慣れ合うつもりは無いぞ」
「ワタシは、脱ぎ合えれば満足デス」
相変わらず、互いに一方通行の会話。鍛錬場にて、模擬戦用の木刀を構えたふたりの打刀が相対している。村正を横目でうかがってみたところ、一見普段と変わらない様子に見えた。自分で手合せ当番を指名しておきながら、どのような手合せになるのか全く想像がつかなかった。
判定係の蜂須賀虎徹が開始の合図を出そうと口を開く。その時、何かを思案している様子だった大倶利伽羅が「待て」と遮るように声を上げた。そこに居合わせた皆が何事かと彼の方を見ると、大倶利伽羅は一瞥もせずに木刀を鍛錬場の隅に放り投げ、代わりに腰に下がっている真剣を抜いた。
「虚飾は不要だ。脱ぐと言うからには、これが望みなんだろう」
刀の切っ先が灯りを反射して鋭く光った。それを鼻先に突き付けられた村正は、しばらく呆気にとられた表情をしていたが、やがて心得たとばかりに唇の片端を上げて挑戦的に微笑んだ。
「上等デス」
その答えを受けて、大倶利伽羅はわたしに視線を寄越した。真剣での手合せは審神者の許可と立ち合いが無ければ認められない。その規定を気にしてのことだろう。わたしは大倶利伽羅に分かるように、構わない、と合図を出した。
今度こそ、手合せ開始の掛け声が響く。刀を薙ぐために一歩踏み出す瞬間、俯いた大倶利伽羅の口の端もわずかに上がっているのが見えた。
「終わりか。手を抜いたつもりはない」
「…………そうでしょうとも。本気で折られるかと思いました」
「真剣で良いと請け合ったのはそっちだ」
村正は、そうでしたね、と若干口を尖らせて相槌を打ちながら、衣装にまとわりつく埃を払った。
「……デスが、不思議と楽しめましたよ」
晴れやかな声を聞いて、大倶利伽羅はやっと村正の方に顔を向けた。彼はしばらく手合せの相手を見つめたのち、「そうか」とだけ返事をしてそれきり顔を背ける。そして、隅の方に転がっていた二本の木刀をきちんと回収し、そのまま鍛錬場を出て行ってしまった。
村正はその背を見送ってから、わたしの方を振り返った。双方怪我は無いようですね、と確認すると、この通り、と言いたそうに両腕を広げてみせる。わたしは村正の左腰に下がった刀に目を留め、先ほど使った真剣を見せてくれるように頼んだ。
「どうぞ。先ほどの手合せで、刃こぼれなどはしていないと思いマスが」
わたしは頷いて刀を受け取る。もちろん刀の状態の点検も兼ねているが、わたしの目的は他にもある。慎重に刀を抜き、刀身を鍛錬場の明かりに透かした。考えてみれば、こうして抜き身の刀をじっくり眺めるのは随分久しぶりだった。
「良い刀ですね」
そう呟くと、村正は一瞬虚を衝かれたように目を瞠ったが、すぐに誇らしげに「当然デス」と胸を張った。わたしはそのまま柄を軽く捻り、刀の角度を変えた。そのたびに、眩暈を覚えるような独特の輝きが生まれては消えてゆく。もともと感想を伝えるつもりではあったのだけれど、わたしの口からは思った以上に自然に言葉が滑り出てきた。
「こうして光にかざすと、板目肌がよく分かりますね。流れるような地鉄の紋様が美しい。棟の形状は庵棟で、刀身の反りは浅く、鋩子の返りは小丸。刃文はオモテウラが綺麗に揃っていて……」
「…………」
「切っ先近くの直刃と中腹からの乱れ刃の対比が興味深い。それと――ああ、これですね。刀身の腰の辺りに、特徴的な二つの箱刃が」
「あの」
そこまで言ったところで、村正が口を挟んだ。鍛錬場の向こうの方で話をしていた蜂須賀と浦島も、何事かとこちらに注目している。村正は彼らのほうを気にしつつ、幾分声を潜めて困ったように言った。
「あのデスね。面と向かってそういうことを言われるのが、ワタシたち刀剣男士にとってどれだけ気恥ずかしいことか分かりマスか?」
え、と思わず訊き返す。村正は口許に手をやり、まだ何か言いたそうに視線を彷徨わせて口ごもった。どこからか桜の花弁が降ってきて、刀を持つわたしの手の上に一片落ちた。それで初めて、彼が言わんとすることを理解した。
「ああ……成程。失礼」
そのまま刀を鞘に収め、両手で彼のもとに返した。彼は刀を受け取りながら、いつもの含み笑いを唇に乗せて満足気に口の端を上げる。
「デスが……悪い気はしませんね」
そう呟いて、鞘に収まったままの刀を軽く天に掲げた。つられるように刀の切っ先の方を見上げていると、村正はその視線に気付き、ふと笑ってわたしに向き直った。
「今回は模擬戦でしたが、実戦刀は戦場でこそ輝くもの。アナタの為に、もう一度この刃を振るいまショウ。さあ、次の出陣先は何処デス?」
*
十二月十日。わたしの部屋まで戦績を持ってきてくれた獅子王が、文机の脇に積んである書籍を指差して言った。
「主、これ全部読み途中か?」
歴史書に事典、鑑賞指南書など、刀剣関連の書籍がほとんどだ。わたしが普段よく読んでいる戦術書等とは毛色の違う書名が並んでいたので、珍しいと思ったのだろう。
「調べ物をしていたのです。あらかた読み終えたので、書庫の方に仕舞っておかないといけませんね」
ちょうどお茶を淹れ直しに厨に行こうかと思っていたところだ。ついでに、少し回り道をして書庫にこれらを返してこようか。そう考えて本の山を抱え始めると、獅子王は「へえ」と相槌を打って、書籍を半分持とうとしてくれた。
「どいつのこと調べてたのか知らないけど、刀剣を深く知ろうとしてくれるのって、きっと嬉しいと思うぜ」
「そうだったらよいのですが」
彼の真意に近付こうとして、村正と人間の縁について調べてはみたが、彼の意を汲むことができたのかどうかは未だに分からなかった。ただ、午前の出陣でしっかり誉を総取りしてきたところを見ると、少なくとも昨日の手合せは良い刺激になったようだ。
書庫と厨をまわって用事を終え、獅子王と別れた後、わたしは書類を取りに行くために二階の執務室へ向かった。すると、階段を上がる途中で、執務室の前の廊下に人影があることに気付いた。その刀剣男士は何か作業をしている風でもなく、ただ胸の前で腕を組んで窓の外に目を遣っている。
「村正。誰かを待っているのですか?」
話しかけてみると、村正はわたしに気付いて腕組みを解いた。
「いえ。アナタに声を掛けようと思っていたところデス」
そう言ってわたしに軽く笑いかけ、廊下の窓の外を指差す。
「そこの川べりまで、散歩でもしませんか」
午前中は雪が降っていたが、積もるほどではなかったようだ。川べりの道の枯れ草の上を乾いた風ばかりが吹き抜けていた。わたしたちは水面の波紋を眺めながらしばらく黙って歩いた。辺りには、砂利を踏むふたり分の足音だけが響いている。
やがて、村正が白い息を吐いて話し始めた。
「この間、ワタシに訊きましたね。桃源郷という言葉から思い浮かべるのはどのような世か、と」
わたしは外套の襟をかき集めて頷いた。村正はそれを確認し、少しだけ唇の端を上げて続ける。
「あの時、一瞬だけ夢見てしまったのデス。ワタシにとっての理想の世を。……誰にも妖刀などと忌み嫌われぬ世界を」
わたしの分の草履の音が止まった。村正は数歩分進んでから、わたしが足を止めたことに気付いて振り向いた。わたしはそこではっと現実に立ち戻り、少し足を早めて彼に追いついた。
「けれど、刀剣男士としてのワタシは、刀剣・千子村正が纏う妖刀伝説から生まれた存在。であるならば……」
村正はそこで言葉を切ったが、続けて何を言おうとしているかはよくわかった。千子村正が妖刀と呼ばれない世界は、彼がこうして刀剣男士に成ることができなかった世界だと言いたいのだろう。
「妖刀という言葉は、人間の歴史と、モノである自分とを繋ぐ絆のようなものなのでショウね」
そう言うと、彼は寒空に自分の手を翳し、掌を返したり指を曲げてみたりして、人の体が動くのを冷静な眼差しで観察し始めた。そして、最後には指を順番に閉じて、何かを握り込むように固く拳をつくった。
「でも、それがワタシにとっては絆に思えた。妖刀という言葉こそが、自分をこの世に縛り付ける枷だと思っていました」
――絆という字は“ほだし”とも読む。馬の足に絡ませる足枷のことだ。
わたしが何も言えずに彼の横顔を見つめていると、村正はふと目元を和らげ、ゆるく広げた自身の両腕を見下ろした。
「……あの子ども、村正の短刀を家宝だと言ったんデスよ。細い両腕で、嬉しそうに抱えて」
わたしは彼が何のことを話しているのかを悟った。家宝だというその短刀は、その子どもの親か先祖が主君から賜ったものなのだろうか。村正の話から、嬉々として短刀を見せたがる子どもの姿が目に浮かぶようだった。
「ワタシの目には、それが希望の光に見えました。けれど……」
村正の瞳に宿った光が翳り、声色も階段を順に下るように深く濃く翳ってゆく。彼はその調子のまま、息を白く染めながら淡々と語った。
「あの短刀が……ワタシの仲間が砕けたのを見た時、自分自身が内側から変容してゆく感覚がありました。自分の一部を失って、その穴を何とか埋めようとして血肉が蠢いているような。足元が揺らぐような感覚でした。それが何だったのか、今なら分かる気がしマス」
「自分が、変容する……」
わたしは思わず反芻した。村正はわずかに歩を緩めて頷き、一言ひとことゆっくりと噛み締めるように言葉を紡いだ。
「そうデス。結局、ワタシが恐れていたのは、自分が自分でなくなること、だったのかもしれません」
村正の低い声を聞いていると、彼が怪我をして帰って来た日の様子が、その切実な声がまた脳裏に蘇る。
わたしは相槌の代わりに、「村正」と呼びかけてその場で立ち止まった。村正もつられて立ち止まる。
「もしも、この先、自分がどういう存在であるかをまた見失いそうになったら」
彼の心のうちの真意に触れた今、伝えたいことはひとつだった。わたしは彼を見上げて笑いかけた。
「そうしたら、またこうやって話しましょう。あなたが千子村正という名で、刀剣男士で、仲間がたくさんいて……わたしの大事な刀だということを、何度でも証明しますから」
彼をこの世に縛る絆ではなく、心をすくい上げてこの世に繋ぎ止めるよすがとなれたら良いと思う。そう、かつてこの本丸の皆がわたしにそうしてくれたように。
村正は目をしばたたいた後、「はい」と柔らかい声で一言答えて微笑んだ。
わたしたちは散歩を終え、来た道をまた辿るように連れ立って本丸へ歩き始めた。途中で万屋に続く分かれ道を通ったので、このあいだ話題に上った甘味処がこの道の先にあるという話をした。次の買い出しの帰りにでも立ち寄ってみようと提案すると、村正は笑って了承した。
本丸に帰り着くまでの間に、立ち止まったり後ろを振り返ったりすることはもう無かった。正門の前に着く頃には辺りは暗くなり始めていて、ちょうど門の周りの掃き掃除をしていた歌仙が「おかえり」とわたしたちを迎えてくれた。
わたしは村正と一度視線を交わし、ふたりで声を合わせて答えた。
「ただいま戻りました」
十日語り
一日目
――この本丸で起こった何気ない出来事を、今日から十日間、書き記してみようと思う。
二月二十日。わたしは執務室で書類を処理しながら、規則的に聞こえてくる金鋤の音に耳を傾けていた。中庭で鶴丸が穴を掘る音だ。誰かを驚かせようとしているのだろうけれど、あんなにも白昼堂々と穴を掘る姿を見せていては、引っかかるものも引っかからないだろうに。それでも誰かが落ちて驚くことを期待して一生懸命下準備をしている姿を想像すると、我知らず笑みがこぼれた。
さて、脱線はこのくらいにして、早めに今日の分の報告書をまとめてしまわなければならない。今日の出陣は午前中のみ。行先は元禄時代の江戸、編成は骨喰藤四郎に、大和守安定に、日向正宗に……。
報告書が九割がた埋まった頃、階段を上がる足音がして、近侍が室を訪ねてきた。
「鍛刀が終了しましたよ」
投入した資材の配合から予想するに、今回は脇差か打刀か……。新しい戦力が期待できそうだ。
「わかりました。ありがとう」
わたしは一旦筆を置き、近侍を伴って鍛刀場に向かった。
二日目
二月二十一日。今日は数少ない審神者友達の一人と審神者会議で偶然遭遇したので、互いに軽く近況を報告し合った。たまたま会議に連れて行った清光と、向こうの本丸の一番刀である陸奥守は、本丸あるある話で意気投合したようで、最終的にはわたしたちよりも盛り上がっていた。友人とはまた電話で連絡することを約束し、万屋の煎餅をお土産に買って帰った。
ちなみに、昨日の鍛刀でやって来たのは大脇差のにっかり青江だった。結局錬結のための素材になったのだけれど、ちょうど鍛刀場の前を通りかかったらしい青江が「おや、僕がいるねえ」と冗談なのか真面目なのか分からない調子で笑っていたのが印象的だった。
三日目
二月二十二日。天気が良いので、足袋のまま縁側から足を下ろしてしばらく日向ぼっこをすることにした。わたしは時々縁側で思索に耽ることがある。何を考えているかというと、次の出陣の編成や、刀剣男士の育成方針の策定、刀装の在庫管理の方法、今日の夕飯の献立……そんなようなことだ。個人的には、執務室に籠るより、こうやってただ中庭を眺めている時のほうが良い考えが浮かぶ確率が高い気がする。
早春の空に溜息をついていると、廊下の向こうの方から軽い足音が近付いてきた。
「主。お茶が入りました」
平野藤四郎は折り目正しく一礼してその場に膝をつき、わたしの隣に菓子盆を置いてくれた。わたしは一旦立ち上がり、広間から座布団をもう一枚持ってきて、「一緒にどうですか」と平野を座布団に座るように促した。
「はい。ありがとうございます」
お茶好きの平野は、遠慮しながらも嬉しそうに座布団に座った。焙じ茶と煎餅に、星の粒のような金平糖を添えて、昼下がりのちょっとしたお茶会が始まった。
四日目
二月二十三日。今日はわたしが厨当番だったので、味噌汁を作ることにした。太郎太刀に味見を頼んだところ、ちょうど良い塩加減で美味しいとお墨付きを頂いた。普段は米味噌を使うことが多いけれど、今日は太郎太刀の地元から取り寄せた豆味噌を使ってみたのだ。それを彼に説明していたら、明るい話し声とふたり分の足音が厨に近付いてきた。
「五鈴さんに、太郎太刀さん。おはようございます! 美味しそうですね、お味噌汁ですか?」
「おはようさん。やった、早朝から畑仕事で腹がぺこぺこだぜ」
顔を出したのは、物吉貞宗と後藤藤四郎だ。わたしはふたりに挨拶を返してから、思わず彼らの顔と手元の味噌汁を交互に見た。そして、双方の繋がりに気付いた瞬間、何だか自然と笑みを誘われた。きっと単なる偶然だろうが、もしかしたら尾張名物のこの豆味噌の香りが彼らを引き寄せたのかもしれないという考えが浮かんだのだ。
「……どうかしましたか、主よ」
太郎太刀は、この人がなぜ今笑い出したのか分からない、とでも言いたげな目をして、隣で冷静にわたしのことを見ていた。
五日目
二月二十四日。今日は夢見が悪く、夜中に突然目が覚めた。と言っても、夢の内容を鮮明に思い出せるわけでもない。夢とはえてしてそういうものなのかもしれない。あんなに現実感のある夢だったのに、目が覚めればたちまち色も音も匂いも煙のように消えてしまう。ただ確かなのは、寝床の中で起き上がった今、ひどく心拍数が上がっているという事実だけだった。
再び寝付けそうもないので、水でも飲もうかと厨に足を運んだ。意外なことに、厨からは灯りが漏れていて、誰かが動いている気配がした。わたしが厨の暖簾をくぐると、彼はすぐにこちらに気付いた。
「ああ。誰かと思えば、大将か」
薬研藤四郎はわたしを椅子に座らせ、何か食べるか、と訊いてくれた。わたしは首を横に振った。
「薬研は、夜食ですか?」
そう尋ねると、薬研は頷いて、「そのつもりだったが、俺も飲み物だけにするかな」と薬缶を火にかけ始めた。しばらく待つと、蜂蜜と砂糖が入った牛乳が目の前に置かれた。薬研は、「これしか作れんが、よかったら飲んでくれ」と言ってわたしの向かいに腰掛けた。わたしはありがたく杯のふちに口を付けた。
わたしたちはしばらく牛乳の湯気だけを見つめて黙っていたが、ややあって、薬研が目をこちらに向けて口を開いた。
「……大将。この本丸は……」
わたしも彼と目を合わせて話を聞く体勢に入ったが、薬研はしばらく何かに迷うように言いよどむ様子を見せ、やがて目を伏せて、「いや、なんでもない」と首を振った。わたしが重ねて問おうとすると、薬研は席を立って、わたしの分の杯も回収してくれた。ふたり分の杯は、ちょうど空になったところだった。
「温まったら、早めに寝床に入っちまうといいぜ。そうしたらよく眠れる」
薬研のその言葉の通り、その夜はそれから一度も夢を見ることなく、泥のように眠ることができた。
六日目
二月二十五日。雪景色の朝だった。気温は低いけれど、空気の清々しさと清浄な白一色の景観も相俟って、不快な寒さではない。わたしは綿入りの上着を羽織って縁側に腰掛け、刀剣男士有志が東西陣営に分かれて本気の雪合戦を繰り広げるのを見守っていた。この本丸では、今のところ毎年のように大規模な雪合戦が開催されている気がする。良いように表現するなら、雪国ならではの風物詩、といったところか。
近くで欠伸が聞こえた気がしたので振り返ってみると、薬研藤四郎が通りかかったところだった。わたしはまだ寝ぼけ眼の彼に声をかけた。
「昨夜は不寝番でしたね。お疲れ様でした」
「ああ、お早うさん。大将はよく眠れたか?」
いつも周りに目を配ってくれる彼らしい気遣いだった。わたしは「ええ。お蔭様で」と答えて、今日くらいはもう少し寝んでいてはどうかと彼に勧めた。薬研がそれに答えようとした時、誰かが投げた雪玉が彼の後頭部に見事に当たった。薬研は頭の後ろに手をやって状況を把握すると、「よーーし、待ってろ」と悪戯っぽく笑い、無造作に下駄を引っ掛けて雪合戦に参加し始めた。
七日目
二月二十六日。今日の出陣先は幕末の会津だ。編成は、陸奥守吉行、秋田藤四郎、不動行光、蜻蛉切、愛染国俊、堀川国広……。戦果は上々。特に愛染は、途中で拾った資材を両手で持ち切れないほど抱えて、元気一杯に帰ってきた。
出陣の成果を報告書にまとめ終わると、自然に溜息が出た。無意識に片手で顔の半分を覆う。そのまま、壁に掛かっている日めくりに目を遣った。――あと三日。たった三日だ。今日が火曜日ということは……今週末には、全てが終わる。
八日目
二月二十七日。
今日は仲間のひとりにとって大事な日だ。わたしは足りないものは無かったかどうかを何度も点検したのち、満を持して彼の見送りに立った。感傷的な雰囲気を嫌う彼らしく、旅立ちは思ったよりもあっさりしたものだった。
「……彼には、大きな覚悟があるようですね。きっと、更なる強さを得て戻られるでしょう」
隣で前田藤四郎がわたしに話しかけた。わたしは「そうですね」と頷いて、旅立ちの後ろ姿が見えなくなってしまうまで、じっとその姿を見送った。彼らを送り出す時には、こうして必ず後ろ姿を目に焼き付けるようにしている。個人的な願掛けのようなものだ。
前田と一緒に屋敷の中に戻り、廊下に掛けてある暦にふと目をやった時、なぜか今日が水曜日だった気がして一瞬心臓が跳ねた。準備の慌ただしさに曜日感覚を失って、定例の審神者会議を連絡も無しに欠席してしまったかと心配したが、今日が二十七日だから……よかった、会議は明日のはずだ。わたしは心から安堵の溜息をついた。
九日目
二月二十八日。「政府から報せが入ったよ」と小夜左文字が巻物を持って来てくれた。わたしはそれを受け取り、巻物の文字の上に指を滑らせて一つずつ点検していった。現在この本丸に顕現している刀剣男士ひとりひとりについて、詳しい戦績と各種データが記されている。
巻物に目を通していくと、やがて或る刀剣男士の項目に行き当たった。そこを指でなぞった時――前触れも何もなく、ひどい家鳴りのような音が耳元で響いた。何の音かを分析するより前に直感した。きっと、何か硬いものに罅が入る音だ。今までに、何度も――いや、本当に何度も聞いたのだろうか。わたしは、何を、忘れて――
口許にやった指が震えているのに気付いた。わたしはそれを振り切るように無理やり壁掛けの暦のところに足を運んで、今日の分の日めくりを捲った。二十八の数字が消えて、大きく二十九と書かれた紙が現れる。――そうか、今年は閏年だから、二月二十九日が存在するのか。わたしは、まるで自分の身体と精神が分かたれてしまったかのような浮遊感のなかで、ぼんやりとそんなことを考えた。
十日目
三月一日。欠伸を噛み殺しながら正門に繋がる前庭の掃き掃除をしていると、門のところに一つの人影が見えた。時間遡行のゲートが開く音がしたから、遠征に遣っていた刀剣男士が帰って来たのだろう。わたしは門の方に向かって彼を出迎えた。ゲートを通ってきた刀剣男士は一振り。千子村正だった。近付いて顔をよく見ようとすると、彼ははっとしたように夕日のような目を見開き、一瞬、落ち着き無く視線を彷徨わせた。ひどく疲れたような顔をしていた。
「お帰りなさい」
わたしは彼を見上げて話しかけ、「先に御守りを預かりましょうか」と掌を差し出した。村正は懐から袋を取り出して、わたしの掌の上に置いた。赤い紐を二重叶結びにした小さな御守りだ。
わたしは、少しそのまま待っているようにと村正に伝えて、一度屋敷の方に戻った。御守りを執務室の棚に仕舞い、非番だった岩融を伴ってまた正門に向かう。村正はまだ心ここに在らずといった様子だったけれど、わたしの声が聞こえてはいるようだ。勝手にどこかに行ってしまうこともなく、先ほどと全く同じ姿勢でわたしを待っていた。
「村正。屋敷の中へ」
わたしが手を差し出して誘おうとしたその時、すぐ近くで鋭く風を切る音が聞こえた。何事かと見上げると、目の前に打刀の切っ先があった。正確には、その刃はわたしに向けられてはおらず、千子村正の首元に添えられていた。
隣で岩融が薙刀を構える音が聞こえた。わたしも真剣での戦闘が繰り広げられることを覚悟したが、千子村正は刀の柄に手を掛けもしなかった。その気力が無いように見えた。代わりに、彼に刃を突きつけている者が彼の背後で口を利いた。少なくともわたしはこれまでに聞いたことがない、氷のような声音だった。
「――ワタシの主に何の用デス?」
その後、わたしと岩融とで修行帰りの村正を説得したところ、彼はまだ腹に据えかねるといった様子ながらも渋々刀を収めてくれた。彼が真新しい戦装束を纏っているのに対して、この本丸に迷い込んできた千子村正の衣装はところどころ破れたりほつれたりしていて、よく見ると腕や足には軽傷相当の怪我をしていた。わたしは何も訊かずに彼を手入れ部屋に案内した。岩融と石切丸には手入れ部屋の前での見守りを頼んで、手入れが終わったら教えてほしい、と言付けた。
手入れが終わるのを別室で待っている間、村正は一日早く本丸に戻ったわけをわたしに話した。
「アナタ、鳩を飛ばしたでショウ? それで、急いで帰って来たんデスよ」
そうだ、昨日の審神者会議での全体通達を受けて、遠征中や修行中の者を念のために呼び戻しておいたのだった。その通達の内容というのは――
わたしが説明しようとした時、ちょうど石切丸が手入れの終了を教えに来てくれた。
「すっかり傷も治って、一段落したところだ。話す準備が出来たそうだよ」
それを聞いて、わたしと村正は顔を見合わせて頷き合い、屋敷の北側の空き部屋へ向かった。
もう日も高いというのに、小ぢんまりとした室の中はどこか薄暗く、その中にこんのすけと千子村正だけがひっそりと座っていた。室に入ると、千子村正は視線を動かしてわたしたちの存在を認めはしたものの、表情は相変わらず乏しかった。わたしは、自分の本丸の村正とこんのすけも同席させても良いか、と彼に交渉した。彼は予想通り、政府の使いたるこんのすけが同席することを嫌がったが、記録係が必要だと伝えると漸く了承した。
「さて。気分はどうですか」
自分の向かいに座った千子村正に問うと、彼はただ俯いて首を振った。
「上辺の会話は必要ありません。これから、ワタシへの“糾弾”が行われるのでショウ?」
自嘲するような響きだった。こちらの出方を試すように様子を窺う彼は、わたしの隣に背筋を伸ばして座っている村正とは対照的に、憔悴しきった顔色をしていた。
「いえ、糾弾までは。あくまで、何があったのかを確認したいだけです」
まずは事の始めから説明せねばならないし、彼にもそうしてもらわねばならないと思った。わたしは身体の向きをわずかに斜に変えて座り直し、ふたりの村正に向けて言った。
「――昨日の審神者会議で、全体通達がありました。ある本丸で異常事態が起きていると。この事象が他の本丸に与える影響を最小限に留めるため、もし遠くへ派遣している刀剣男士がいれば今日のうちに極力呼び戻し、戦力を本丸に固めて有事に備えておくように、と」
わたしの隣で、村正が「そういうことでしたか」と小さく溜息をついた。もうひとりの千子村正は、まるで人形のように身動ぎひとつしないままわたしの話を聞いていたが、突然「その『異常事態』の通達内容は……」と口を開いた。
「“審神者を斬った刀剣男士が逃走している”。そんなところデスか」
それを聞いて、こんのすけの耳がぴんと立った。わたしは肯定も否定もせず、ただ客人に茶を勧めるように彼の方へ片手を差し出した。張り詰めた空気の中に衣擦れの音が響いた。
「話してくれますか?」
数秒の沈黙の後、千子村正は無言で首肯し、ひとつ息をついた。それから、氷の上の一歩目をゆっくりと滑り出すように、彼の本丸の話を語り始めた。
「……最初は、運用歴のわりには顕現させた刀剣男士が少ない本丸だと思いました。逆に言うと、気になったのはそこだけで、他には特に問題があるようには見えませんでした。審神者の霊力も十分でしたし、物腰が柔らかく、冷静沈着で……人間性の面では寧ろ好感すら抱いたことを覚えていマス」
彼は苦々しげな表情で言った。後悔と自分自身への苛立ちが声音に滲んでいた。
「ワタシにとっての初陣は、山伏国広が隊長で、ワタシの他の部隊員は和泉守兼定だけでした。任務は滞りなく完了しました。ワタシ以外の二振りの練度を考えると、この合戦場では手応えが無さすぎるのではないかと思ったくらいデス。しかし――その日を最後に、山伏と和泉守とは会えなくなりました。ぱったりと姿を見なくなったのデス。審神者に尋ねても何のことだとはぐらかされ、他の刀剣男士に聞いても、みな首を横に振るか口を噤むだけでした」
「出陣させられると、次の日から姿が消える……」
わたしが顎に手をやって呟くと、千子村正はわたしの方を見て頷いた。
「しばらく経つと、和泉守とはまた会えるようになりました。デスが、それはワタシと一緒に出陣した和泉守ではない。鍛刀で新しく顕現された、別の和泉守兼定でした」
わたしと村正とこんのすけは、何かを確かめ合おうとするように互いに顔を見合わせた。千子村正は更に話を続けた。
「これまでの小さな違和感が、頭の中で繋がり始めました。共に生活する刀剣男士の数が少ない。それも、短刀や脇差が比較的多く、太刀や大太刀の数は少なくて、薙刀にはついに一度も出会わずに終わりました。そして、数日前に会話した内容について誰に尋ねても、心当たりがない、という返事が返ってくる確率が異様に高かった……」
千子村正は刀剣男士の数を指折り数える仕草をして、やがて諦めたようにその両手を膝の上に下ろした。語る声はまた一段と硬くなった。
「疑念が確信に変わったのは、不寝番を任されていた夜のことでした。審神者の居室の前を通りかかった時、聞いてしまったのデス――鶴丸国永らしき声と、彼の刀身に罅が入る音を。審神者は聞き慣れた穏やかな口調のまま、鶴丸に絶えず何かを話しかけていました」
わたしは彼の話に口を挟まないようにして時折相槌を打っていたが、思わず「その話の内容は?」と質問した。千子村正は長い髪を揺らして首を傾げた。
「さあ……。かろうじて聞き取れたのは一言だけでした。おまえは練度が上がりすぎた――そう言っていました」
室の中がしんと静まり返った。わたしを含めた全員が何も言葉を発せなかった。ややあって、村正が冷静な声で「それで」と続きを促した。千子村正は目を伏せて語り続けた。
「翌日、審神者を問い詰めましたが、要領を得ない話ばかりで煙に巻かれ、それより遠征に行って資材を集めてくるようにと命じられました。ワタシは質問を変えて、練度が上がった者から順に折られるのならワタシを折らないのは何故か、と尋ねました」
彼の声と重なるように、障子戸が二・三度震えて音を立てた。風が吹いてきたらしい。
わたしは、その審神者の返答はどうだったかと訊いた。千子村正は歯噛みするように言葉を絞り出した。
「顕現させづらい刀だから、今のところは残しておいてやる、と」
それを聞いて、わたしの本丸の村正が眉間に皺を寄せたのが視界の端に見えた。
「あなたのように顕現させるのが難しい刀剣男士以外は、一定の練度に達したら命を奪われ、また鍛刀などで顕現させた刀剣男士が新たにやってくる……。そういう仕組みだったわけですか」
千子村正はわたしの見解を肯定し、昔を思い出しているような声で続けた。
「みな、最初は何も知らずに審神者を慕い、本丸に馴染もうとしていました。そして、この本丸の異常さに気付く頃には、審神者の手で……」
声はそこで途切れた。わたしは彼が話を再開する気があるかどうか少し待ってから、水を向けるように「時の政府には?」と質問した。
「ワタシは近侍だったので、戦績を見る機会もあったわけデスが、あの人、審神者としての評価は高かったようデス。まあ、ひとえに生まれついての霊力の高さのお蔭でショウね。あの地区の中では、あの人よりも霊力が安定している審神者はそう見なかったそうデスから」
彼は審神者への侮蔑を隠しもせずにそう吐き出し、冷たい声で「あんな者を高く評価する政府に期待はできません」と結んだ。隣にいるこんのすけの耳が深く垂れ下がっていった。わたしは何も言えず、村正に話の続きを促した。
「その日から、ワタシは半ば強制的に単騎遠征に出され、帰って来た時には、また本丸の顔ぶれは変わっていました。審神者に報告に行く途中で蜻蛉切とすれ違ったので話を聞くと、昨日は久しぶりに出陣させていただけて練度も上がったのだ、と言っていました」
「それは……」
「そうデス。その夜、ワタシは寝ずに審神者の室を見張ることにしました。しかし、いつの間に連れて来たのか、気付いた時にはもう室内から審神者と蜻蛉切の声が聞こえていました。ワタシが急いで室の障子を開けると、目の前で――」
わたしは唇を引き結び、袴の上で揃えた手を強く握り込んだ。千子村正はそれを一瞥し、一呼吸置いて続けた。
「一瞬でした。自分が真剣を抜いてあの者に向けたところまでは覚えていて――あとは、何か生温い物体が畳に転がっているだけ。そんな認識でした」
彼は茫洋とした目で自分の両の掌を見下ろした。そして、まるで何かに憑かれたように淡々と話し続けた。
「血溜まりのなかで、蜻蛉切の呻き声が聞こえて我に返りました。彼は、少し前の不寝番の時に主の寝室の前で聞いてしまったという内容を今わの際に教えてくれました。『わたしが最も優れていなければならない』『誰も彼も自分を馬鹿にしている』『わたしよりも強い者を全て折ってしまえばよい』『おまえたちの代わりなどいくらでもいる』――そんなようなことを、まるで人が変わったような口調で取り乱しながら口にしていたと。だから、主を救って差し上げたかったのだ――と」
命が消えゆくなかで、それでも何かを伝えようとする蜻蛉切の姿が目に浮かぶようだった。千子村正がその目で見てきた光景が、そのまま映像としてわたしの脳内にも共有されているような錯覚をおぼえた。
「蜻蛉切はワタシに頼みました。生きて、真実を外の世界の誰かに伝えてほしいと。――ワタシはそれを聞いて、本丸の門の外に出ようという気になりました。すぐに防犯装置が作動して警報音が鳴り続けましたが、気にならなかった。当て所もないまま時間遡行経路のなかを彷徨い続け、やがて出口のようなところが見えたので、そこから外に出てみました」
「そこが、この本丸の前だったということですね」
千子村正はまた黙って頷いた。それで彼の話は終わりだった。
聞けば、彼の本丸があった時代は二二〇〇年代で、所属地区もわたしの本丸とはまるで違ったそうだ。そんな接点の無い本丸同士が時間遡行経路を通じて繋がることは有り得るのかとこんのすけに尋ねると、「有り得ないことではないですね」との返事だった。
「当代風に言うなら、電波の周波数がたまたま合ってしまった、という表現が近いと思います。本丸内の部屋の配置が似ていたり、審神者様同士の霊力の波長や生活習慣が似ていたり、たまたま同じ刀剣男士が近侍を務めていたり……そういった共通点がある場合、繋がりやすくなるということはあるようです。もちろん、頻繁に起こっては困るので、警備システムで制限をかけてはいますが」
そういえば、へし切長谷部が修行に出ている間、わたしの本丸でも一時的に村正を近侍としていた。もしかしたら他にも似ている点があったのかもしれないが、こと今に至っては、それが判ったところで詮無いことだし、これ以上の調査と事実確認は政府側に任せるしかない。審神者殺しについても同様で、一時的に保護しただけのわたしたちが踏み込めるのはここまでだ。わたしはもう彼から話を聞き出すのはやめて、疲れが癒えるまで少しここで休ませてから、政府の担当者に連絡を入れて引き渡すことにした。
それを彼に説明して、寝床を整えさせますから、とわたしが立ち上がると、彼はわたしを呼び止めて、躊躇いがちに尋ねた。
「なぜ、こんな親切を? ワタシは……この本丸の千子村正のふりをして、アナタを騙そうとしたのに」
本心からの疑問のように聞こえた。わたしは表情を緩めて答える。
「でも、わたしたちを害そうとはしなかったでしょう」
彼は肯定とも否定ともつかない表情でそっぽを向いた。その反応を確認して、わたしはついでのように付け足した。
「それに、騙されてはいないので特に問題ありません」
そう、あのとき千子村正の御守りを真っ先に回収したのは、最初の違和感から導き出した仮説が間違っていないことを確かめるためだった。わたしが修行前に村正に渡したのは、赤ではなく青い紐で結んだ御守り袋だったからだ。
わたしを見て瞬きをした千子村正を残し、わたしたちは室を辞して静かに障子を閉めた。そのまま、室の外で控えてくれていた石切丸に、あと少しの間だけ見張りを頼まれてくれると助かる、と託けた。
その後、引き渡しと事情聴取と後片付けをひととおり終えた頃には、もうすっかり夜になっていた。湯を使って寝室に戻り、長い一日だった、と今日の出来事を思い返していた時、急に日記の存在を思い出した。机の抽斗から日記を取り出し、何となしに頁を繰って、ここ最近の日記の内容を読み返してみる。二月二十日の頁は空白だ。二十二日や二十四日の頁も同様だった。どうやら直近の約十日間は、ちょうど一日おきに日記を書いていたようだ。昨日は本当なら、早朝から鶴丸が目をきらきらさせて、新作の落とし穴を見てほしいとわたしを裏庭に連れ出したことを書いておきたかったのだけれど、審神者会議での例の通達を受けて慌ただしく対応に追われていたら、いつの間にかそのまま一日が終わっていた。……ということを、せめて今日の分の日記にこうして書き足しておくことにしよう。
いつの間にか、室の外から静かな雨音が聞こえていた。午前中は確か小雪がちらついていたから、雪解けの雨といったところか。わたしは寝室から縁側に出てみた。すると、向こうの廊下の角から村正が歩いてくるところだった。彼は自然にわたしの隣に並ぶと、雨のそぼ降る中庭の様子を一緒に眺め始めた。そうしてしばらく経った頃、村正が「……今日のことデスが」と徐に口を開いた。
「何が真実かはともかく、ワタシは……彼の身に起こったことを、全くのひとごとだとは思いません。あれは、有り得たかもしれないワタシの姿でもあった。否、彼もワタシも千子村正という同位体のうちの一振りに過ぎないのだから、まさに言葉の通り“ひとごとではない”のデスが」
村正は雨を眺めながらそう話した。雨だれの先の、もっとずっと遠くの方を見つめているようですらあった。わたしはその横顔を覗き見て、ただ話を聞いているということだけを示すために頷いた。雨音が沈黙の隙間を自然に埋めてくれた気がした。そうしているうちに、本来であればもっと早く伝えたかった用件があることを思い出し、そういえば、と改めて彼の方に向き直った。
「村正。順番が逆になりましたが、先ほど、三通目の手紙を読みました」
村正は「ああ」とだけ答えて、少しだけ決まり悪そうに目線を外した。……確かに、自分が送った真面目な手紙の話を目の前でされるのが気恥ずかしいという気持ちはわたしも分かる。けれど、わたしは今日だけは敢えてその反応を見なかったことにして、この話題を続けることにした。
「やっと、呼んでくれましたね」
何のことかは言わなくても伝わる自信があった。彼は虚を衝かれたように目を見開いた後、目元を和らげて頷いた。
「あの時、アナタが言った通りでした」
今度は、わたしが何のことかを考える番だった。わたしが訊き返す前に、村正は晴れやかな声で続けた。
「“ワタシは何者なのか”――その答えがはっきりと分かったから、こうして帰ってきたのデスよ」
わたしは村正を見上げて微笑んだ。しばらく前に彼に伝えた言葉が脳裏に蘇ってきたからだ。
彼は姿勢を伸ばし、わたしに向かって丁寧に一礼した。防具同士が擦れて涼しい音を立てた。
「ただいま戻りました。主」
返す言葉は決まっている。ここがあなたの居場所だ、と証明するための言葉。
「お帰りなさい」
村正は安心したような顔をして、「旅の間、ずっと脱ぐのを我慢していたので肩が凝りました」といつもの調子でぼやいた。
その後もいくつか言葉を交わしてから就寝の挨拶をした。彼と別れた後、雨の匂いの中にかすかな花の香りを感じて振り向いてみると、ちょうど彼がいた辺りの場所に、一足早い桜の花弁が二つ三つと舞い落ちるところだった。